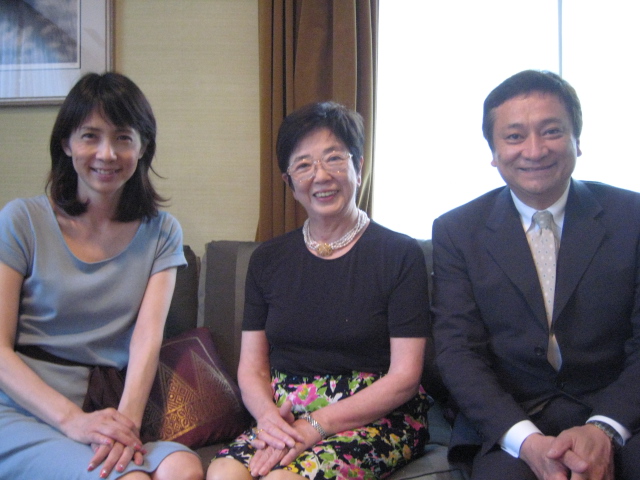プロフィール
59年、教養学部卒業。結婚後は大使のご主人と共にマレーシア、アメリカに駐在を経験。自身でも東京家庭裁判所調停委員、エイズ予防財団理事・副会長、アジア婦人友好会会長、都心の新しい街づくりを考える会委員その他数多くの団体の要職を務める。
- 齋藤
- 2009年の春にICUで開催された桜祭りで、栗山さんが3期生の代表として、ICU設立時に献金して下さったアメリカ人についてお話をされたのですが、すごく良いお話で感動しました。そのこともあり是非このインタビューでも栗山さんのお話を伺いたいな〜と思ったんですよ。今日はよろしくお願いします。栗山さんのご主人は駐米大使という要職に就かれていましたが、そんなご主人の内助の功というのでしょうか、大使の奥様というのは非常に重要な役割を担っておられますよね。
- 栗山
- 夫とは一緒に働くことが多く、内助というのか外助というのか…両方ともやっていました。特に夫がアメリカ駐在の終盤は私も外に出ることが多く、ずいぶん忙しかったことを思い出します。よくアメリカの友人達から、「日本は良いですね、大使が二人いるようなものですね」と誉め言葉のつもりで言っていただいていたりしたのですが、それは私にとっては、一種反省の材料でした。出しゃばりと思われているのかなって。「こんなことを言われてはいけない!」と思って、「大使は一人です、私は影です!」と伝えるようにしていました。しかしやはりアメリカでは影だけでは済まないんですよね。当時大統領夫人であったヒラリー・クリントンのように女性がどんどん表舞台へと出ていく時代でしたので、“私もヒラリーにならって、裏だけでなく表でも夫を支えなければ!”という気概で、必要なことはどんどんさせていただいたと思います。
- 齋藤
- しかし、簡単におっしゃいますが、栗山さんがやってらしたことはすごく難しいことだと思います。普通の人ではなかなか出来ませんよ。
- 栗山
- 外務省というのはある意味で特殊な職場です。社交の場も多く、人とのつき合いが、国同士のつき合いの下支えにもなっていくわけです。その際、にこにこと後ろから付いていくだけではなく、一緒に学んで出来ることは一緒にやって欲しいというのが、結婚したときからの夫の意向でした。夫の大使時代には、私はワシントンではミミのサロンというのを開いて(ミミというのは私のニックネームで、夫も外国の友人もそう呼んでいたのですが)、多くの分野のアメリカ人との交流を深めるお手伝いをしました。地方に出かけるときには、大使とは手分けをする意味で、私は小学校や中学校を訪ねて、日本の話をしたりインタビューに応じたりしながら、子供達にも日本に対して親しい思いを持ってもらおうと努力いたしました。また、ボランティアをしている老人方の話を伺い現場を見せて頂いたり、日本人墓地を尋ねたりと、私自身、とても得るところが多かったと思います。帰国後は、その経験をなるべく多くの方々とシェアするべく、頑張ってまいりました。今は世の中は役人バッシング、外務省バッシングの方向が強く、働いている皆さんも大変でしょう。またバッシングをされてもやむを得ないと見えるところも確かにあって、そこは気をつけなければならないと思います。しかしその反面、世の中に役立つ部分、役立たなければいけない部分というのも山ほどあり、それは、外務省に入ってから本当に一生懸命勉強いたしました。
- 齋藤
- それは、ただ闇雲に努力してもダメですよね。栗山さんの場合はご結婚される時は既に旦那様は外務省におられたわけですが、ご結婚されてから、「外交官の奥さんになったから、こういう風に自分自身を磨こう」と意識されたことはありましたか?
- 栗山
- ありますよ。卑近な例では語学ですね。いくらICUで英語をやっていても、それだけでは、現地で追いつきませんでした。結婚後の夫の最初の任地がニューヨークの国連代表部で、1964年、娘が生まれた3か月後に娘を連れて初めてアメリカに行きました。それから、必死で英語を勉強しましたね。
- 齋藤
- それは、どういったやり方で勉強なさったんですか?
- 栗山
- 国連事務局の中に外国人向けの学校があるので、そこの夜学に通ったのですが、周りを見回してみると外交官が多く、奥さんはいらっしゃいませんでしたね。ですが、“恥をかくのは今だ!”と思ったわけです。まだ20代でしたし、年を重ねてからは、なかなか恥はかけないじゃないですか。おかげさまで、後のワシントン滞在時、大使の夫人となってからも、数多くのスピーチの機会をまぁまぁ無事にこなしたと思います。また、現地の人のやることをよく見ていたのも一つの学びの努力だったと言えるのではないでしょうか。なるべく外を見て、世間を見て、アメリカ人の話し方や人付き合いの仕方、日本人が良く思われているところ、悪く思われているところを感じとるよう意識していました。それは自宅にいてはできない学びですよね。
- 栗山
- そういうものがありませんでしたので、ワシントンから帰ってきた後(1978年)、本省で「外務省夫人のための会」を立ち上げました。本省勤務後の夫の海外赴任先はワシントンでしたが、当時、ニューヨークの国連本部で働いていたのは皆外務省員だったのに対して、ワシントンは外部の方も沢山いらした大所帯だったんですね。研修所で色々と勉強してきた方もいらっしゃいましたが、でもその勉強してきた中身が現地の現実と食い違っているところも、見ていると沢山ありました。やっぱり現地での生活を体験した人が、次に行く人たちのためにもしっかりと本当のことを伝えていかなければならないと思い、「子女教育を考える会」、「夫人のための会」の二つの会を立ち上げて、会長をやらせていただきました。
- 齋藤
- それは2つとも本省でやられていたわけですよね。前例もありませんし、本省の方は、びっくりされたのではないですか?
- 栗山
- いえ、前例がなかったからこそ本省の方も協力してくださいました。もちろん最初はちょっとびっくりしたと思うのですが、「確かにそういった部分は自分たちではなかなか出来なかったから、助けてほしい」ということで、本省と一緒に協力してやっていました。
「優雅でなければならない」と、白鳥のように水面下で必死に足を動かしていました。それは、表では見られちゃいけないんです。
- 渡辺
- たまたま私の母親が初期の日航の客室乗務員で、日本人がまだ外国にあまり行っていなかった時代に空を飛んでいたため、渡航先で大使や奥様方の大変さを生で拝見したと話しておりました。「大使ご夫妻というのは、もちろん表立たれるのはご主人だけれども、奥様と正に二人三脚で外交を支えていらっしゃるのよ。大使夫人と言うと優雅に聞こえるかもしれないけれど、パーティーにお招きする時は奥様が、『日本食で喜んでいただけて、しかも食べやすいものは…』など考えながら沢山の焼き鳥を串に刺して準備をしたりもしていらっしゃるのも拝見したわ。」と。
- 栗山
- それはそういう職業ですので仕方がないですよね。夫人としてやらなければいけないことは色々あります。でも実はそれが結構楽しいんですよ。色々な方達とお会いする機会も多く、助けられたり、助けたり。私は日本でも外国でも、私の経験させていただいた国際交流ということで、ずいぶん色んなところから講演やスピーチ、大学での講義等を頼まれました。そういえば、ひとつ、すごく珍しい申し出がありました。読売新聞のカルチャーセンターで、「外交官夫人というものについて話をしてほしい」という依頼で、お受けするかどうかをすごく迷ったのですが、「外交官夫人という存在は誤解されている部分も多いからこそ、もう少し良く分かって頂きたい、裏も表も理解してもらいたい」と思い、お受けしました。
- 渡辺
- 事実、エリートだから、という側面もあるでしょうけれど、身近な存在ではない分、あまりにも誤解されていることも否めないのでしょうね。
- 栗山
- 誤解されているからこそ分かってもらわないといけないと思っています。特に大学の講義などでも「これから国際社会に出ていく人たちに向けて、外交官夫人としての経験を大学生に伝えることで何かのお役に立つことが出来れば、そしてまた、これから若い人たちが海外で働くに際して、お互いに学び合えることもあるのではないか」との思いで引き受けてきました。
- 渡辺
- これまで栗山さんご自身、どういった部分が誤解されていると思われましたか?誤解されていると感じられたことは多かったですか?
- 栗山
- 多いですね。例えば、公金と私金の使い方については、私たちは普段の生活の中に公のお金が入ってこないように、すごく気をつけていました。マレーシア時代は特に、出納の責任者が自分自身でしたので、買い物から帰ると、すべてのレシートをテーブルに並べて、「これは公金」、「これは私金」と一つ一つ分けて計算するところから始まっていました。手伝ってもらっていたコックさんには、「こんなことをする前に自分はじゃがいもの皮をむき始めたい、これでは食事の時間に間に合いません!」と言われていたのですが…。そのコックさんが結婚したので、奥さんをプライベートで雇い、レシート分けを手伝ってもらうようにしましたが、それでもまだ分かりにくい部分はありましたね。例えばパンを3つ買ったとします。「公」につけると文句を言われることがあるんです。良く解釈されると、「料理の中につなぎとして入れ込んだり、飾りとして使ったりしたのだろう」と理解してもらえるのですが、そうでない場合は、「パーティーのパンだったらもっと沢山使うはずだ、これは翌日あなたたちが朝食に食べた分だろう?」と言われます。これはとても小さな例ですが、自分たちの行動ひとつひとつが善意で解釈されるか、悪意でとられるかという難しさはあり、そこをクリアーにするために皆大変な努力をしていました。
- 渡辺
- そういったことは、実際にお話を伺わないと想像すらできない部分が沢山ありますね。
- 栗山
- そうかもしれません。でもそういうことは裏側の話で、私自身、外交官の夫人、特に大使夫人というのは、今はやりの「日の丸を背負って」ということでもあり「優雅でなければならない」と心がけて、自分を演出してきた部分もあります。パーティーの準備で焼き鳥に串を刺すところは見られてはいけない、人様に会うときには、きちんと皆さんに目配り気配りをしなければならない、と意識してきました。それはまるで水鳥と一緒で、表舞台で優雅であるために、裏では必死で足を動かしているんです。その足の動かし方というのは若いころから、教わりながら勉強しないとなかなか出来ないと思います。
- 齋藤
- 栗山さんのご経験は、外交官の奥様に限った話でなく、海外という異文化に行ったときに、日本人のご夫人としてどういう風に振る舞うことが大事なのか、というところにも通じるのではないでしょうか?
- 栗山
- それは確かにおっしゃるとおりです。ただ若干別の部分もあるかもしれません。外務省は昔から、パーティーを開いて人とのつき合いを深め、国と国との友好を深める努力をしています。と同時に、良い日本の文化を紹介する、そして日本人の伝統に根ざした考え方や、人間としての共通の部分を理解してもらうという目的もあるので、時代の変わった今でも、みんな頑張っています。それこそ、高級なものをだしたり、着飾ったりということは必要でない時代になりましたので、色々な方々とお会いして話を楽しみます。我々の目的を持って開くパーティーの他に、アメリカの人たちに頼まれて大きなチャリティーの会も引き受けたりもするのですが、私は、小さな宝でも藁でも良いから、何かをつかんでこそやる意義があると、ただ言われたようにやるのではなく、日本のためになる何かをやっているという目的意識を持って協力してきました。お金や労力を使ってやるパーティーなので、お客様共々学ぶ機会なくして資金調達のお手伝いだけには会を開催しないという意気込みです。例えば盲導犬のためというなら、どのような訓練をして役に立つ仕事をしているのかを実際見せていただきながら日本の話をつけ加える、またケア物資のためのものをやるときには、私が子供の時に学校給食で、この粉ミルクや薬でどんなに助けられて嬉しかったなど思い出話を先ず披露して、心を寄せ合いながらパーティーを始めるなど、その時々でずいぶん趣向や話題を考える努力をしてきました。本当に沢山の機会が与えられましたが、今思うととても懐かしく、みんなと一緒に楽しみながら沢山の宝物を拾い、種もまけたのではという満足感でいっぱいです。そういった部分は少し特殊な環境かもしれませんね。
色々と目立つ活動をしていたので、マスコミから批判されることも多くありました。でも、今振り返るとその苦しみなんて小さくて、ここまで進んでくる中で、沢山の方が助けてくださってきたんです。
- 齋藤
- 栗山さんはアメリカに行かれた時なんかもずいぶん努力されて、一生懸命頑張ってこられたと思いますが、挫折されたことや、難しいな、と思われたこと、逆境と感じられたこともあると思います。それはどういったことなのでしょうか。
- 栗山
- 今思い出してみるとそういうことってほとんどないんです。多くの方々に助けられました。ただ、今でも嫌だなと思うのは…、マスコミの取り上げ方ですね。私は、よく「豚もおだてりゃ木に登る」、だから批判も仕方がないけれど、もっと応援して欲しいと言っていました。
- 渡辺
- それは…思い返されるのも嫌かもしれませんが、どういうところが一番問題だと思われますか?
- 栗山
- 私は色々な活動をしており、比較的目立っていた外交官夫人だったのですね。大使館で国際交流のためのサロンを主催したりもしていて、例えばメリーランド大学の大学院生が日本に来るための奨学金もそこから生まれたりしました。そういったことをやって、目立っていたからこそ、出る杭は打つというか…日本のマスコミも叩きたくなったのだと思います。週刊誌に取り上げられたりもしたんですよ。
- 渡辺
- 実際に取材されることもなく、ですか?
- 栗山
- ありませんでしたね。例えば、ある総理夫人を空港までお迎えにいく日に赤いコートを着ていたのですが、「スポットライトをあびるのは総理夫人なのに、何で大使夫人があんな派手なコートを着ているんだ」って、それだけで批判されました。「何でそんなことを週刊誌が書くのだろう」って思いました。グレーや紺のコートでしたらきっと目立たなくて良かったのかもしれませんが、私の持っていたグレーのコートは毛皮がついていたんですね。その頃はちょうどアメリカでは毛皮が批判されており、毛皮は絶対にやめてくださいと言われていまして。そのグレーのコートの隣にあった赤のコートはチャリティーで買ったものだったということも思い出し、それにしたわけです。アメリカ人は日本人と比べてチャリティーへの意識が高くて、同じお金を払うのだったら他の人に還元されることに価値を見出すのですよね。
- 渡辺
- マスコミとの関わりで嫌な思いをなさったことが多々あるにも関わらず、私のようにマスコミで働いている後輩にもお話をしていただいて本当に感謝申し上げます。きっと、今仰った以外にも理不尽な思いをなさったことは、数々あるのでしょうね。
- 栗山
- ただ、そういったことに関する苦労は今振り返るととっても小さなことで、今まで歩んで来た中で、助けてくれた方のほうが周りにとっても多いんです。むしろ、日本のマスコミの関係者には、大いに感謝しています。アメリカの新聞や、マレーシアにいたときには、マレーシアの新聞や雑誌ですが、華やかによい記事を沢山書いてもらったりもしました。マスコミとのおつきあいも良いこともあり、がっかりすることもありでしたが、豚も上手に木に登れるようになったとすっかり錯覚する場面すら、多くあったのは事実です。華やかに、存分に働かせていただきました。
- 渡辺
- 私自身、マスコミに籍を置きながら、反省する点は多々あります。小さなことを過大に報道する場合があったり、その分、別の側面からの取材がおざなりになったり、結果、期せずして人を傷つけてしまうという事実は否めないと実感します。電波や紙やインターネットが人を責めたり、糾したり、裁いたりする機能も権限もないと思う一方で、観察するという正確な機能は持っていてほしいと願っています。アメリカでは何代も通して大統領を取材している記者が定点観測のような存在としているのは良い例かもしれませんが。栗山さんは、外交官夫人という位置からアメリカをずっとご覧になっていて、今のアメリカについてどう思われますか。
- 栗山
- やっぱりアメリカは自由な国ですよね。ヒラリー・クリントン氏とオバマ氏が争うというようなことは、日本ではなかなか考えられません。アメリカの一番の傷口は人種で、あれだけの差別をしてきた歴史があり今もまだ修復しきれていない部分もある中でオバマ氏が大統領になったのは、本当に素晴らしいと思います。ただ、まだやはりアメリカにも閉ざされている部分も沢山あるので、そういった部分は開いていって欲しいな、という気はしますね。
ICUは、色々な考え方が全部認められるような大学でした。「1+1は2かもしれないけど、もしかしたら違う展開もあるかもしれない」、そういった考えも許される、自由に発想させてくれる学校だったと思います。
- 齋藤
- ところで、栗山さんは小さい頃はどんなお子さんだったんでしょうか?
- 栗山
- 父が裁判官でしたので小学校は6回ほど変わっています。小学校5年のときに最高裁が出来、父が最初の裁判官になりましたので、それからはずっと東京に住んでいたのですが、東京に来てからはすごく厳しい女の園で育ちました。それでも私は一日中体操着を着て、窓から外に出ていくようなおてんばな子だったのですが。「そんなことしてはなりません!!」って怒られたりしていて。
- 齋藤
- その奔放さは、ご家族の影響もあったのでしょうか?ご兄弟はおられるんですか?
- 栗山
- 年の離れた姉と、弟一人と妹が二人ですね。
- 齋藤
- 皆さんも栗山さんのように活発な方たちだったんですか?
- 栗山
- 元気な人たちでしたね(笑)。
- 齋藤
- ということは、お父様よりお母様の血をつがれたのでしょうか?
- 栗山
- いえいえ、父はすごく厳格ですが、だからといって活発でないわけではなく、スポーツ万能な人でしたよ。東大ボート部に所属していて、ゴルフも上手でしたし。
- 齋藤
- なるほど。しかしそれだけ小さい頃から活発だった栗山さんなので、学生の頃から色々な活動を積極的にやられていたのでしょうか?
- 栗山
- 学生の頃からひらめきが多くて色々なことを考えついていましたね。ICUは自由な大学で、色々な考え方が全部認められるような大学でした。「1+1は2かもしれないけど、もしかしたら違う展開もあるかもしれない」、そういった考えも許される、自由に発想させてくれる学校だったと思います。
- 齋藤
- そもそも何故ICUに入ろうと思われたんですか?3期生というと、当時は誰も知らなかったのではないのでしょうか?
- 栗山
- 実は私も知りませんでした。
- 齋藤
- 栗山さんは、どちらのご出身ですか?
- 栗山
- 東京ですが、東京にいても知りませんでしたよ。私は日本女子大付属の小学校から高校まで通っていたのですが、大学は共学に行きたいと思っていたんです。しかしうちは堅い家なので、「共学なんてとんでもない!そんな所に行ったら嫁の貰い手がない!」と父から大反対されました。でも東大を受けるつもりでこっそり勉強していて…。そんなある日、父がICUの情報をどこかから仕入れてきて、「これからは、日本人でも国際的な視野で仕事をしたり、生活したり出来るようにならなければいけない。それを学ぶのにとても適したICUという素晴らしい大学があるから、そこだったら共学の大学でも良い、受けなさい」と言われたんです。
- 渡辺
- 裁判官だったお父様は様々な情報網を持っていらして、ICUはお父様のアンテナにひっかかった大学だったのですね。
- 栗山
- そうですね。私は理系だったので「ICUでは理系の勉強は出来ない…」と当時は思っていたのですが…。でも、せっかくICUに行き、将来国際的な分野で働いていこうと思うならば、勉強するのは理科じゃないな、と考えるようになって。
- 渡辺
- ではICUでは理学部を志されなかった?
- 栗山
- その時は学部というものがありませんでした。入学してから自分で学びたいものを選ぶことが出来たんです。
- 渡辺
- 大学にお入りになった時の実感としては、いかがでしたか?
- 栗山
- とても楽しい大学でした!すごく明るい学校で、その時はまだ人数がとても少なかったですね。女の子が50人、男の子が100人。それはアメリカの教育の経験上、「男女共学」と言っても半々ではなく、この比率が一番良い、と決まっていたみたいです。
- 齋藤
- そうなんですか!?今のICUは7割が女性になっているので、えらいことですね(笑)。
- 栗山
- でも、女の子が強いから、「そのうち女子大になるね」、と、その頃から言われていましたよ(笑)。
母が「英語を話すなんて嫌だし、外人の居るパーティーなんて行きたくない!」と言うので、父が小学校5年生の私を進駐軍のパーティーに連れて行ったんです。それが、夫のお姉さんと出会ったきっかけでした。
- 渡辺
- 今、机の上に置いてくださったICUの3期生が編集なさった本(注1)を拝見していると、栗山さんのページに、アドバイザーの秋田先生からのご結婚祝いのスピーチが載っています。「男だったら秀才と言ってあげるのだが、女だからその言葉は遠慮しておきます」と。これはおそらく栗山さんをよく現しているのでしょうね(笑)。栗山さんは、ご主人とはいつ出会われたのですか?
- 栗山
- 彼は私の憧れの人でした。夫の父も最高裁の裁判官だったので、小学校5年の頃に彼を初めて知りました。当時はあまりよく知らなかったのですが、親同士は親しい知り合いで、親戚を通しても関係がありまして。
- 渡辺
- お家同士のご交流があったのですね?
- 栗山
- 彼にはお姉さんがおり、小学校の頃は彼女とお付き合いがあったのです。まだ進駐軍の時代でしたので、進駐軍のパーティーもよく開かれていたのですね。姉は私と一回り違うので、堂々とパーティーに行ける年だったのですが、私の場合は、母が「英語を話すなんて嫌だし、外人の居るパーティーなんて行きたくない!」と言うので、仕方なく父が小学校5年生の私をパーティーに連れて行ったんです。その時、栗山の姉がよく面倒を見てくれていまして。
- 渡辺
- ご主人のお姉さまを先にお知りになったんですね。
- 栗山
- そう、知り合った後に弟がいるということを知って、彼が東大に入ったと聞き、「へー、すごいですねー」と話していました。それから彼は大学3年のときに外務省に入って。卒業してないので、私は今でも時々「高卒」って言ってからかっているんですけどね(笑)。
- 渡辺
- 実際に親しくおなりになったのはいつ頃だったのですか?
- 栗山
- それはもうずっと後で、実際に結婚するという話になった時ですね。彼は外務省の研修でアメリカに行っていましたし、その後の転勤先もブラジルだったこともあって全然会う機会がなかったんです。
- 渡辺
- その間も、ずっとご主人が憧れの方だったわけですよね。
- 栗山
- そうですね。おまけに、夫の父が、私が大学に入るときの保証人でして。ICUって入学時に親の他に保証人が必要でしょ。父が、「栗山さんに頼んだらいいと思うよ」と言って、お願いしました。
- 齋藤
- 10歳のときにお父様と一緒に進駐軍のパーティーに行かれていたということは、小さな頃から色々な人との接し方をずっと学ばれていたんでしょうか?
- 栗山
- 終戦が小学校3年の時だったのですが、それまではアメリカ人なんて獣のように言われていて、「恐ろしい奴らだ」ということだけを叩き込まれていました。だからそれまでは、外国人、外国文化に接するという機会にものすごく欠けた時代でしたよ。
日本は困っている人を見ても手伝いを申し出るのが何だか気恥ずかしかったり、なかなか他人と自由に接するのが難しかったりしますよね。ロスは、日本とは異なるアメリカ人のホスピタリティの文化に触れて感動した、思い出深い場所です。
- 渡辺
- 私たちは、自分たちの生まれる前の話は歴史の教科書やドラマ、映画、小説などで「こんな時代だったんだ」という大きな時代背景やエピソードとして知ることは出来ますが、実際どんな苦労や努力が個々のレベルであって今に至ったかを知るのはなかなか難しいと思います。華麗なる一族やスーパーエリートのように物語の題材になるようなケースでも。ですから、栗山さんのような方にお話を伺えるのは貴重な機会だと思っています。
- 栗山
- そういった努力をする機会があったことに対して、むしろ私は大変感謝しています。実は私は、アメリカのシェナンドー大学の名誉博士号を持っているんです。もちろん私自身今まで努力はしてきましたが、でも大学という場所で勉強をせずに博士号をもらえた私はとてもラッキーなんですね。ICUの苦学生の話等を読ませて頂くと本当にその努力の量に頭が下がりますが、私にはこのような、降ってわいた幸運が多いので、「まだまだ努力が足りないな、周りへの感謝を忘れちゃいけないな」と、ことあるごとに思っています。
- 渡辺
- 栗山さんご自身は、努力をなさるしかない環境に身を置いていらしたのだろうな…と思います。
- 栗山
- 今となっては楽しかったことしか思い出せないですよ。でも、色々なことをやってきましたが、「行きたくない、したくない…」と、始まる瞬間まで思っていたことも多々ありました。
- 渡辺
- ICUを卒業なさってからご結婚までは、何か仕事をしていらしたのですか?
- 栗山
- 日立製作所の海外事業部に居たのですが、その当時なので全然面白くなくて2年間で辞めました(笑)。その後、親を継いで法律家になろうと思って、「私、お嫁になんて行かなくて良いから、お父さまの後を継いであげる」と宣言し、毎日家にこもって六法全書の勉強をしていたんです。でも夫と結婚することになり、「司法試験なんて受けても何の役にも立たないよ、それより英語とフランス語をやって!」と言われて、「これ幸い」と思って勉強を辞めちゃったんですよ。
- 渡辺
- そんなお二人はどんな結婚式を挙げられたのでしょうか?最高裁の裁判官二人というお父様方がいらっしゃるわけですから、かなり華やかなお式だったのではないかと想像申し上げますが。
- 栗山
- 私たちは親がそれぞれに45歳の時の子供だったのでその頃は二人とももう引退していました。でも親の関係者は沢山居て、裁判官、夫の外務省の先輩、私の友人や先生など、当時としては人数の多い、150人ちょっとの立食のパーティーでしたね。最初は帝国ホテルの孔雀の間をとってあったのですが、結局、開館したばかりのホテルオークラ平安の間になりました。
- 渡辺
- 新婚時代、お嬢さまのご誕生直後に日本を離れられたんですよね?
- 栗山
- 当時は飛行機の気圧の問題で子供が3か月にならないと渡航できなかったので、夫は先にアメリカに発ち、私は娘が3か月になってから行きました。その時初めてアメリカという国に行ったのですが、当時は到着までに一泊しなければならなかったので、入国手続きをホノルルでやるためホノルルに泊まるか、本土に入ってから泊まるか悩み…結局ロスで一泊したんです。そのとき、初めてのアメリカの夜にアメリカ人の本当に暖かいホスピタリティに触れたのは、今でも忘れられません。
- 渡辺
- どんなホスピタリティだったのでしょうか。
- 栗山
- 泊まったホテルで、夜、娘を連れて下の食堂に行き、食べやすそうだったハンバーガーを注文したのですが、娘を抱えていると、実際は食べるのもままならなくて。そしたら、年取った女性の方が二人きて、「その状態で食事をするのは大変だから、あなたの夕飯が終わるまで私たちが見ていてあげますよ」と言われて。
- 齋藤
- 娘さんを預けられたんですか?
- 栗山
- ええ。今だったら心配する人も多いのでしょうが、当時ですし、私の根本は性善説なので、何の疑いも持たずに「ありがとう」と言って隣に座っていた彼女たちに娘を渡して、お話ししながらお食事をさせていただいたんです。ハンバーガーを食べ終わって娘を返していただいて、本当に有難かったです。「こんなに親切なのか!」って感動して。日本は困っている人を見ても手伝いを申し出るのが何だか気恥ずかしかったり、なかなか他人と自由に接することが難しかったりするじゃないですか。私の様子を見て、気遣ってくださった彼女たちに、もう本当に感謝で一杯でした。夫が大使になってから、ロスの日米協会主催の何百人もの人が集まる大きなディナーがあったのですが、そこで、「乾杯の音頭はMrs.栗山にしてもらいます」と言われたんですね。大使の夫人という立場の人が乾杯の音頭をとるというのはアメリカでもすごく珍しいことなのですが、こういったすごく思い出深い経験のある、しかも初めて降り立った地なので、喜んで引き受けました。当然冒頭にこのエピソードをお話しして、温かいアメリカンホスピタリティーに接したことにお礼を申し上げました。
マレーシアについての著作は、出版社の社長に直談判して出来た本なんです。毎日深夜までワープロに向かって、1日50ページの原稿を書いていました。
- 齋藤
- 栗山さんはご自身で本も出版されてらっしゃいますが(注2)、拝見すると、1986年の暮れにマレーシアに行かれたと書いてありますね。89年の2月に本が発行されているということは、向こうにおられる間に本を書き上げられてしまったということですか?
- 栗山
- いえ、マレーシアに居たのは1年半だけでした。
- 齋藤
- ということは、1年半の間に経験されたことを帰国後すぐに本に書いたということですか?
- 栗山
- はい。日本へ帰国後、マレーシアで感じたことを活字にして伝えたいと思い、サイマル出版の社長に「会ってください」と電話をしてみたところ、運の良いことに会って頂けることになりまして。そこで、「マレーシアについて、もっと多くの日本人が知るべきです!」と熱弁をふるってきたわけです。そしたら、「確かにあなたの言う通りだと思うので、検討するためのプロットを作って持っておいで」と言って頂いて、そのプロットが採用されて編集者をつけてくれて…、そうやって出来た本なんです。執筆をする段階になった時にその社長に、「こうした本って大体どのくらいの期間で書き上げるものなのですか?」と伺ったところ、「3か月で出来る人もいるし、1年かかる人もいますよ」と言われたので、「よし、じゃあ私は3か月以内でやってやろう!」と思い、書き上げました。夜中までワープロを使って、一日50ページずつ書いて、一か月で原稿を上げましたよ。編集、レイアウトにちょっと時間はかかりましたが。
- 渡辺
- 「マレーシアのことをもっと分かってほしい、もっと多くの人に伝えたい」という気持ちだけで出版社に直談判して本の執筆という大仕事をやるということはなかなかないケースかと 思います。素敵な本の成り立ちですね。
- 栗山
- 体験記というと「自分はこういったことをしてきた」ということを綴っている本が多くて、それは好きではありません。それよりも、その国の人との交流がどういうものであったか、どんな文化だったか、読んでくださる方が今後マレーシアに行かれることがあったらどんな交流を持ってほしいか、そういうことを伝えたくて。サイマル出版も、「元マレーシア大使夫人が書いた本ならもしかしたら売れるかもしれない」と思ったのかもしれませんし、私のことを「面白い人だ」と思ったのかもしれません。実際のところはどうだったのか分かりませんが、そういう機会を頂けて得しちゃいました。
小さな頃に毎日読んでいた偉人伝と、ICUの文化の二つが、自然に、「人の役に立つことが嬉しい」という考え方を作ったんだと思います。
- 渡辺
- ICUを卒業して、海外で働く方、公務員になる方、さまざまいらっしゃいますが、その中で、“専業主婦”という道を選ぶ方も勿論いらっしゃいます。専業と簡単に言いますが、主婦業を24時間して、お給料はない。もちろん男性も頑張ってらっしゃいますが、勤務時間、仕事の中身がある程度決まっています。でも、主婦の場合は無尽蔵ですよね。子供を見て当然、ご飯を作って当然、家を綺麗にして当然、お客様の相手をして当然…。換金されないものの方が当然じゃないのは自明の理なのに、私なぞ専業主婦に敬服する面ばかりです。でも、栗山さんの場合は、ご主人を支えて二人三脚をなさりながら夜学に通ったり執筆なさったり、ご自分の時間をその他にも使ってらっしゃる。本当に驚きます。
- 栗山
- それは私がちょっと変わった人間なのかもしれないですね。ICUの文化かもしれませんが、結婚して、相手に全部預けるのではなく、自分を持ち、やりたいことは実現したいと思って、夫と一緒に学んできました。夫も、私が別の仕事をすることに賛成で、下の娘が大学に入った後に働き始めました。 夫の仕事の手伝いもあり時間のやりくりに苦労しましたが、家庭裁判所の調停委員をしたり、テレビの仕事も何回かいたしました。またアメリカから帰国後は、アジア婦人友好会の理事長として、アジア大洋州24カ国の婦人方や、子供達の教育、福祉のために10年間働かせていただきました。先ほど“No Pay”と仰いましたが、それはどうでも良くって、役に立つことがあるというのが私にとって大事なことなんです。Payされてもやりたくない、能力がないっていう場合もあるわけでしょ。Payされることがなくても、それをやって人が喜んでくれるならば私も喜んでやりたいと思うんです。今でもエイズ予防財団の副会長、国立感染症研究所の倫理委員、新しい都市を考える会の理事など、普通の人の意見も聞きたいと言っていただいて、何らかでもお役に立てるよう努力をしています。
- 渡辺
- そういった考えも、ICUで学ばれたことなのでしょうか。
- 栗山
- それもありますし、子供の頃に学んだ部分もあるかもしれませんね。小さな頃は、読む本がなかったので、自宅の倉庫から父が出してくれた昔の本を読んでいたのですが、それが、国内外の偉人伝だったんです。その中には、「自分が得しよう」と思った人は一人もいません。「何か創造的なことをしたい」と思ったり、「人の役に立つことが嬉しい」と思ったり、そういう人が多くて、それを繰り返し毎日読んでいたので、なんとなくそういった考えが身にしみついていたのだと思います。
- 齋藤
- それはいつごろの話ですか?
- 栗山
- 小学校の時だったので、戦時中か戦後まもなくの話ですよ。そういう子供時代があって、大学もまた、人に奉仕をすることを教えてくれる大学だったので、「人に喜んでもらわなきゃいけない」と意識していたのではなく、自然にそういう考え方を身につけたということではないでしょうか。「他人の役に立つならば頑張ってみよう」と素直に思うようになりました。ほんとはお役に立ってないかもしれないですが(笑)。
「枯れたヒマワリ」のように、枯れてからもなお、お役に立てることはあると思うんです。
- 齋藤
- よくこのインタビュー記事を読まれる方から、「読んでいて元気をもらうんですよ」という言葉をもらいます。世の中で成功されている人も沢山の苦労をされて今のようになられたわけなんですね。栗山さんは逆境をあまり感じたことがないと仰っていましたが、恐らく「人のために」という気持ちが原点にあり、人を大切にし、努力されてきた、それが今の栗山さんを作ってこられたのでしょうね。
- 栗山
- そういっていただけるのは嬉しいのですが、インタビューのタイトルは「今を輝く同窓生たち」じゃないですか。私はもう今は輝いてないですよ、その時代はもう過ぎ去って…(笑)。3期生が編集した本に寄稿した文章のタイトルが「枯れたヒマワリ」なんですが、ヒマワリって、枯れてしまって人を楽しませるという役目を終えた後でも、もう一つ、油を絞られるという役目があるんですよね。主人が公式訪問でアメリカの42州をまわった時に同行していたのですが、その最後の訪問地がノースダコタ州でした。ノースダコタって一面に広がっているヒマワリ畑があるのですが、その時は11月でしたので花はなく、真っ黒に枯れたヒマワリが一面に広がっていて。それを全部刈り取って、芯をしぼって、油にするんですよね。その時、「これがこれからの私の生きる道だ」と思いました。マレーシアに居た時は画家の方に「ヒマワリのようだ」と華やかさを褒められたのですが、今やもうそのヒマワリも枯れてしまっていて、でも、そんな今でもなお役に立ちたい、とうい考えではいるわけです。
- 齋藤
- なるほど…。そんな栗山さんから、最後に、今のICUの学生に対してメッセージをお願いします。
- 栗山
- ICUの学生に関わらず、若い方には勉強して欲しいと思っています。私は勉強が好きで、ICUでも、ものすごく頑張りました。でも、唯一、英語を疎かにしてしまったんです。卒業後、色々なところに行き強く感じたのですが、英語というのは他の語学をやるにしても基礎ですので、後になってとても後悔しました。学生の皆さんには、大学という場で思い切り自由に学ぶことが出来るということをもっと大事に考えてほしいんです。今のICUの人たちも多くの先輩方がそうであったように、「明日の大学」の精神に根ざして、これから皆光り輝いていくことでしょう。学ぶ機会や材料は山ほどある大学なのでそういう面での心配はないのですが、語学の勉強はきちんとなさってほしいと私の反省もこめてお願いいたします。
- 齋藤
- 今日は沢山のお時間を頂戴しましてありがとうございました。
- 注1
- 3期生の卒業50周年を記念して刊行された書籍。栗山さんの寄稿文はこちらへ。
- 注2
- 栗山さんの著書「マレーシアの魅力 人の心の温かい国」は、現在はサイマル出版会がなくなり絶版となっていますが、ICUの図書館にも所有されています
プロフィール
栗山 昌子(くりやま まさこ)
59年、教養学部卒業。結婚後は大使のご主人と共にマレーシア、アメリカに駐在を経験。自身でも東京家庭裁判所調停委員、エイズ予防財団理事・副会長、アジア婦人友好会会長、都心の新しい街づくりを考える会委員その他数多くの団体の要職を務める。著書に「マレーシアの魅力」(92年 サイマル出版会)、共著に「おさかな東西南北」(96年 成山堂書店)、「グローバルフロント東京」(08年 都市出版)がある。