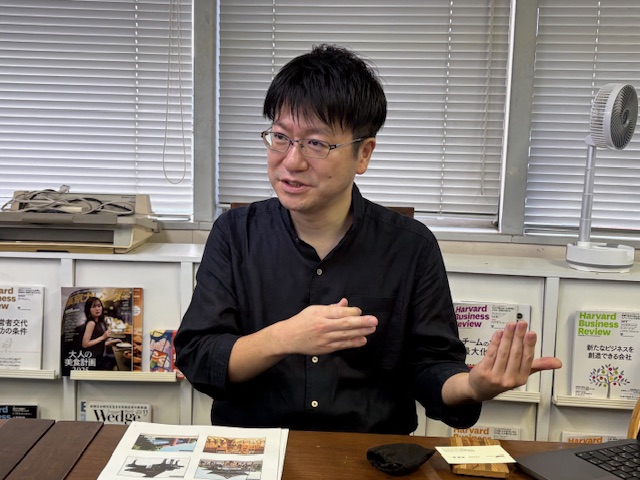プロフィール

2007年、東京・上野の鈴本演芸場で初めて寄席演芸と出会い、魅了される。29歳で出版社を退職。日本では数少ない寄席演芸興行師として、「いたちや」を立ち上げる。以来、伝統芸能と現代感覚を結ぶ活動を展開し、夫である講談師・神田伯山のマネジメントやYouTube番組のプロデュースなど、古典芸能の新たな発信にも積極的に取り組んでいる。
寄席演芸をはじめとした、日本の伝統芸能を次世代へとつなぐことを使命とし、講演や執筆活動も行う。現在は1児の母として育児と仕事に日々悩みながら、「文化の共存と継承」をテーマに多彩な活動を続けている。
- 齋藤
- さて、今回は寄席演芸の興行師として活躍されている、古舘理沙さんのインタビューです。どうぞよろしくお願いします。真理さんから熱いリクエストがあったんですよ。
- 古舘
- そんな…(笑)恐縮です。
- 渡辺
- こちらこそ、ご快諾いただいて感謝しています。ご経歴を拝見して、こんなにユニークで素敵な道を歩んでこられてなんて!と感動しまして。もともとICUに入る前からイタリア語やスペイン語を独学でなさっていて、入学後にラテン語の面白さに魅了されたのですよね?
- 古舘
- はい、そうなんです。実は、私がICUを志望したのは、ラテンアメリカについて学びたくて、ある有名な先生がいらっしゃると聞いていたんです。当時は今のようにインターネットやSNSで情報がすぐに手に入る時代ではなかったので、その先生が入学前に別の大学に移られてしまったことを知らなくて…。入学したら「あれ、先生がいない!」って、最初は困りました(笑)。
- 齋藤
- それは…波乱のスタートでしたね(笑)。でも、ICUでの予想外の出来事が、古舘さんのその後のキャリアに繋がっていると思うと、まさにICUらしい偶然の出会いと言えるかもしれませんね。
- 古舘
- そうかもしれませんね。そのおかげで、2年生の終わりにラテン語の授業を取ることになって、それがすごく面白かったんです。奥深さに惹かれて、そのままラテン語専攻に進んで、西洋古典を専門に学んで卒業しました。入学時はInternational Studies(IS)だったんですが、途中でHumanities(人文科学)に転科したんです。
- 渡辺
- 西洋古典学という専門的で深い学問を修められた理沙さんが、今は寄席演芸の興行師として活躍していらっしゃる。
一見すると、まったく異なる世界への転身ですよね。その背景には、どんな事があったのか、とても興味深いです。
- 齋藤
- そうなんです。普通では考えられないようなその軌跡を、ぜひ今日は古舘さんご自身から詳しくお聞きしたいですね。
- 古舘
- はい、よろしくお願いいたします。
- 渡辺
- ICUを選ばれたのは、どんな理由だったのですか?
- 古舘
- 一番の理由は、ラテンアメリカについて学びたいと思ったからです。きっかけとしては、父の影響で小さい頃からサッカーをよく見ていて、特にマラドーナが大好きで。そこからアルゼンチンに興味を持つようになりました。
- 齋藤
- 当時の日本では、野球全盛の時代でしたよね。お父様がサッカー好きって、珍しいですね(笑)。
- 古舘
- そうなんです。父はちょっとひねくれ者で(笑)。関西人なのに巨人ファンだったり、父の年代ではマイナースポーツだったサッカーに夢中だったり、少し変わっていましたね。
- 渡辺
- ひとりっ子でいらっしゃるとプロフィールに。お父様は、理沙さんと一緒にスポーツを楽しんでいらしたのでしょうね。
- 古舘
- 多分、父としては私が男の子だったら一緒にプレーしたかったんだと思いますが、私は完全に“観る専門”でした(笑)。
サッカーを通してアルゼンチンを好きになって、その背景にある文化をもっと知りたいと思ったんです。ガルシア=マルケスなどのラテンアメリカ文学を、高校生のときに文庫で読んで夢中になりました。それで、スペイン語もラジオ講座で独学して。
- 渡辺
- 独学で?すごい!
- 古舘
- ありがとうございます。そんな流れで、ラテンアメリカを専門に教えている有名な教授がICUにいると知って、「ここで学びたい!」と思って進学を決めました。
- 渡辺
- はっきりと学びたいテーマがあったのですね。
- 古舘
- はい、ただ入学したら、その先生が他大学に移ってしまっていて…。「あれ、いない!」って最初は焦りましたけど(笑)。
- 齋藤
- そんなに明確な目的を持ってICUに来る人って、珍しいかもしれませんね。
- 渡辺
- 他にICUを選んだ理由って、何かありますか?
- 古舘
- あとは、寮があるかどうかは結構大きかった気がします。
- 齋藤
- 寮がよかったのはどうしてですか?
- 古舘
- 東京に行きたかったというのもありますし、ひとり暮らしだったら許してもらえないかもしれないと思って。寮があるからと言えば反対されないかな、という計算です。
- 渡辺
- 理沙さん、ご出身は?
- 古舘
- 私は生まれも育ちも兵庫県西宮市です。大学進学を機に上京しました。
- 渡辺
- ご両親も寮だったら安心なさったでしょうね。寮での生活は、いかがでしたか?
- 古舘
- 最初の一年目は、寮生活を満喫しすぎて、勉強を全然しなくて(笑)。毎日遊び回って、イベント行ったり…。学校に住んでるのに朝起きられなくて学校へ行けなくて、落第しそうでした。
- 齋藤
- 楽しかった証拠ですね(笑)。
- 古舘
- でも、2年生の終わりに転機が訪れました。
- 渡辺
- それが、ラテン語との出会いですか?
- 古舘
- はい。ラテン語の授業を受けて、その沼にはまりました。
- 渡辺
- どんなところに面白さを?
- 古舘
- ラテン語って、西ヨーロッパ言語の文法の基礎となっているので、ものすごく整然としていて、ほとんど例外がないんです。だからこそ、語順が自由なんですよ。たとえば英語で習ったSVOCがVCSOになっても意味が通じる。言語として “完璧な美しさ”に魅了されました。
- 齋藤
- 完璧でありながら自由…すごく不思議ですね。
- 渡辺
- 素晴らしい出会いだったのですね。そのラテン語の沼から、さらに他の言語にも興味が広がっていったのですか?
- 古舘
- はい。西洋古典学専攻は、ラテン語と古代ギリシャ語が必須です。それらの文献を読むには、英語はもちろん、フランス語、ドイツ語も必要ですし、古代ヘブライ語も履修しました。
- 齋藤
- すごい!言語に対する探求心が本当に深いですね。そうすると古舘さんは、何カ国語くらい話せるんですか?
- 古舘
- 喋れる、というほどの自信はもうないんですけれど、カトリック系の中高一貫女子校に通っていたので、フランス語は中学生からやっていました。英語はもちろんとして、古代ギリシャ語とラテン語、古代ヘブライ語、ドイツ語、あとは不純な動機で、ロシア語、イタリア語、スペイン語も頑張って習得しました。
- 渡辺
- 不純な動機、というのは?
- 古舘
- サッカーと、器械体操とフィギュアスケートが好きだったからです(笑)。
- 齋藤
- えー!それはどういうことです?(笑)
- 古舘
- 体操とフィギュアであれば、ロシア、サッカーはイタリアやアルゼンチンの選手の大ファンだったので、万が一どこかで出会って、結婚することになるかもしれないと妄想して、言葉しゃべれた方がいいなと(笑)。
- 渡辺
- すごい探求心!
- 古舘
- 私、ミーハーなんですけど、はまりやすい熱しやすいタイプなんです。一度興味を持ったらとことん突き詰めたい性格で。
- 齋藤
- 熱しやすく、しかも深掘りするタイプなんですね。
- 古舘
- そうなんです。言語だけでなく、あらゆることにそうでしたね。
- 渡辺
- もしかしたら、ご両親も好奇心旺盛でいらっしゃるのでしょうか?
- 古舘
- そうかもしれません。両親は高齢で私を授かったので、とにかく「自立してほしい」という思いが強かったんだと思います。父方の伯母が日大で教授をしていて、当時としては珍しく独身でドイツ留学していたので、両親には「結婚しなくても生きていける」という考えがあったんじゃないかと思います。
- 渡辺
- 「結婚しなきゃ」というプレッシャーがなかったのですね。
- 古舘
- はい。それに親世代はバブル崩壊を経験していたので、終身雇用は当てにできないとわかっていたんだと思います。だから、何でもいいから自分で食べていける手段を身につけてほしい、という考えだったと思います。
- 渡辺
- 勉強は嫌いじゃなかった?
- 古舘
- はい、好きでしたね。でも動機は不純でしたよ(笑)。フィギュアスケーターと話すためにロシア語を覚えようとか。
- 渡辺
- 大学卒業後は、そのまま研究者を目指されたのですか?
- 古舘
- そうですね。専攻していたラテン語の研究を続けたい気持ちもありました。東大の大学院も受けましたが、残念ながらご縁がなくて。
- 渡辺
- あまりに狭き門ですものね。
- 古舘
- はい。でも、落ちたことで「もう十分やったな」とも思えて。そこから「東京で自立して暮らすために働こう」と切り替えるきっかけになりました。
- 齋藤
- ICUで一生懸命勉強して、研究職になりたいと思っていたところが大学院に進めず、そこから一挙にリクルートに就職されたわけですね。意外な展開のように感じますが、何かきっかけがあったのでしょうか?
- 古舘
- 大学を卒業してから、学習塾で中学・高校受験の講師のアルバイトをしていました。
- 渡辺
- 最初は教育の分野でアルバイトを?
- 古舘
- はい。就職活動をしていなかったので、社会にどんな会社があって、どんな働き方があるのか、まったく分かっていなかったんです。働く女性のロールモデルといえば、独身で日大の教授をしていた伯母くらいで、当時の私は漠然と「研究職しか道がないのかな」と思い込んでいた節もありました。
- 齋藤
- なるほど。それで塾講師を選ばれたのは、やはり子どもに教えるということに興味があったからですか?
- 古舘
- そうですね。子どもに英語と国語を教えるくらいならできるかなと思って始めました。ただ、それだけで生計を立てるのは難しくて。それで「私でもできる仕事はなんだろう?」と思い、リクルートに転職したんです。
- 渡辺
- それはまた、どうしてリクルートに?
- 古舘
- そうですね。リクルートなら、いろんな職業を知ることができるだろうと思ったんです。実際に求人営業を経験して、働き方の仕組みがよく分かりました。その経験を通して、「本が好きだから出版で働きたいな」と思うようになったんです。
- 齋藤
- なるほど。本がお好きだったんですね。
- 古舘
- はい。本が好きでしたし、語学の知識も少しは活かせるかもしれないと思って、出版を志しました。ちょうど雑誌編集部に拾っていただけるチャンスがあって、そこから編集の仕事を始めました。
- 渡辺
- リクルートでの営業とは全く違う世界だと思いますが、編集の仕事は面白かったですか?
- 古舘
- 面白かったですね。大変さもありましたけど、編集部での経験は本当に貴重でした。出版業界での人脈とか、進行管理の方法とか、イベントの作り方とか――後に落語の公演を自分でやる時に全部役に立ちました。
- 齋藤
- 具体的にはどんなイベントをやっていたんですか?
- 古舘
- 新潮社で担当していた『Nicola』という中学生向け雑誌で、読者を招いたイベントを運営していました。協賛企業が来て試供品を配ったり、モデルたちがステージイベントを行ったりといった内容です。
- 渡辺
- 当時は、ずっと出版業界でやっていこうとは?
- 古舘
- 最初はそう思っていました。それで『Nicola』の編集部に入れてもらったんですが、すぐに強い違和感を覚えるようになって…。
- 齋藤
- 違和感、というと?
- 古舘
- いまは変わったかもしれませんが当時は、新卒正社員で採用された人しか文芸誌に行けないという不文律があって。私は中途で、正社員でもなく、中学生向け雑誌の枠で採用されたので、異動の見込みがなさそうだとわかったんです。30歳が近づいたとき、ふと「このままずっと中学生向けに雑誌を作り続けて、自分は60歳になっても中学生のトレンドを追ってるのか?」って考えたら、ものすごく不安になって…。
- 渡辺
- なんとなく先が見えてしまったんですね。
- 古舘
- そうなんです。しかも一族経営の会社だったので、極端にいうと、私がどれだけ頑張っても社長になることはない。女性の役員すらいない。自分のキャリアパスもロールモデルも見えなくて、「この仕事とこの会社に人生を捧げられるか?」と考えたとき、答えは“ノー”でした。
- 渡辺
- そこから、落語の道へと?
- 古舘
- はい。落語はもともと趣味でよく観に行っていて、「これなら一生関わっていけるし、好きなことを考え続けて働けるかもしれない」と思ったんです。それがフリーランスになる決断のきっかけでした。
- 渡辺
- 会社員を辞めてフリーランスになるって、ある程度、勇気がいる決断ですよね。不安はありませんでしたか?
- 古舘
- それが、不思議と不安は消えていたんですよね。むしろ、会社員を続けていくことのほうが怖くなっていました。ずっとモヤモヤしていたので。落語の世界に飛び込めば、自分の好きなことだけに集中できる。だったら、やってみたほうがいいと思いました。決断したあとは、逆に気持ちが落ち着いたんです。「これが自分の生きる道かもしれない」って思えました。
- 齋藤
- すごい。その時点ではもう覚悟が決まってたんですね。
- 古舘
- ええ、でもまあ…その後はそれなりに地獄も見ましたけどね(笑)。そんなに理想通りにはいきませんでした。それでも、気づけば人生で一番長い期間続けている仕事になっていて。やっぱり、自分には合っていたんだと思います。
- 渡辺
- そもそも落語との出会いは、どんなきっかけだったのですか?
- 古舘
- 『GQ』時代に一緒に仕事をした映画宣伝会社の方が、「最近落語にハマってる」と言っていて。その場にいたライターさんとフォトグラファーさんも「寄席面白いですよ」というので、「私はまだ観たことがないので、ぜひ連れて行ってください!」とお願いして、上野にある鈴本演芸場に連れて行ってもらったのが最初です。
- 渡辺
- 初めての落語、どんな印象でしたか?
- 古舘
- いやもう、衝撃でした。まず、ビールを飲みながら観てもいいっていうのが信じられなくて(笑)。クラシックバレエみたいに、演者の妨げにならないよう、客席も緊張感をもって鑑賞する文化に慣れていたので、ライブの舞台を見ながら飲食するなんて想像もしてなかったんです。舞台の上では信じられないくらいゆるいマジックをしていたりして、「これでお金をとるの?」って思いました(笑)。『GQ』の編集者として、ヒルズ族だの、海外ファッションだのを追いかけ、必死に時代の最先端にいようと神経を張っていたので、「生きることって、これくらいでいいのかも」と。そこからどんどんハマっていきました。
- 齋藤
- それはかなり意外な出会いですね。でも、観る側から主催する側へ行くのは、かなり大胆な一歩ですよね。
- 古舘
- そうですね。落語にハマると、落語家に弟子入りしたり、女性は三味線をはじめてお囃子さんになったりするパターンが多いんですけど、私は寄席演芸の雑誌に転職できないかな、と一瞬考えたくらいで。
- 渡辺
- その時点では、フリーランスという選択肢は考えていらっしゃらなかった?
- 古舘
- 全然なかったです。でも、落語会を自主企画してる人が結構いることを知って、「それなら自分にもできるかも」って思ってしまって(笑)。
- 齋藤
- それで、「いたちや」を立ち上げたんですね?
- 古舘
- はい、29歳の時です。『牛ほめ』という落語のなかに、「20歳が”はたち“なら、30(さんじゅう)は”イタチ”(いたち)か?」という洒落があって、それにちなんでつけたんですけど、落語家さんたちにもあまり伝わらなかった(笑)。
- 齋藤
- 面白いネーミングですね。立ち上げてからのスタートは順調でしたか?
- 古舘
- 最初の1〜2年は赤字で、貯金を切り崩したり、生命保険を解約したり……本当にギリギリでした。でも、ちょうどその頃Twitter(現X)が流行りはじめて、発信しているうちに少しずつ応援してくれる人が増えてきました。
- 齋藤
- 順調に軌道に乗ったんですか?
- 古舘
- 2010年に独立して、2011年に東日本大震災。寄席演芸にかかわらず、エンターテインメント業界にとっては逆風の年でした。でも3年目でやっと黒字になり、5年目で自宅とは別のオフィスが借りられるようになりました。
- 渡辺
- さっき「それなりに地獄も見た」とおっしゃいましたけれど、どのインタビューだったか、のちに結婚なさる神田伯山さんが、興行師としてスタートなさった理沙さんがどんどん痩せていって。。。と、思い出話としてものすごく物理的に窮状を描いていらしたことを覚えてます。でも、徐々に軌道に乗せつつ、その間にご結婚やご出産も重なったのですよね?
- 齋藤
- 現在の旦那さんとはどう出会われたんですか?
- 古舘
- 私の夫は神田伯山なんですけど、最初はまさかこの人と結婚するとは思ってなかったです。出会ったときはまだ前座で、「20代のぼーっとした男の子」という印象でしたから(笑)。
- 渡辺
- 結婚しようと思われた決め手は?
- 古舘
- 30代半ばになって、子どもが欲しいかもしれないと思ったんです。そうなると、パートナーを真剣に考えないといけない。私はこの仕事を辞めたくなかったので、理解してくれる人が絶対条件でした。
- 渡辺
- 「興行師」って、具体的にはどういうお仕事なのですか?
- 古舘
- ひと言で言えば、公演当日、お客様の前で舞台に上がること以外を全部やるんです。ホール予約、出演交渉、日程調整、チラシ作成、チケット販売、広報、グッズ制作、を全部ひとりでやります。
- 渡辺
- 想像以上に大変そうです…。イベントプロデューサーであり、舞台監督であり、マネージャーであり、経理でもある。全部をひとりで担うってことですよね?
- 古舘
- もちろん、公演当日の受付などは、アルバイトさんをお願いしていますし、伯山が売れて会社にしてからは、社員さんたちが代わりにやってくださるので助かっています。
- 齋藤
- そこまで大変なのに、「やめよう」と思わなかった理由ってなんだったんですか?
- 古舘
- 他にやれることがないと思ってたんです。学者にも戻れない、出版社も違うと感じていた。もちろんアドレナリンで突っ走っていた部分もありますが、選択肢がなかったんです(笑)
- 渡辺
- なるほど。。。理沙さん、何か大きな決断をなさるとき、人に相談したりしますか?
- 古舘
- 基本しないタイプですね。大学受験も進学も就職も、全部親に事後報告でした。「受ける」「落ちた」「バイトする」って(笑)。
- 渡辺
- わかる気がします(笑)。わたしもひとりっ子だからかもしれませんけれど、事後報告できたタイプなので。でも、今はどうですか? 結婚して、お母さんにもなって。
- 古舘
- 今はさすがにしますね。子どものことも、大きな仕事も、夫と日常的に話し合っています。仕事でも家庭でもパートナーなので。
- 齋藤
- それは大きな変化ですね。
- 渡辺
- 以前、記事で「誰々の奥さんと呼ばれることにモヤモヤする」って話していらしことも印象に残ってます。
- 古舘
- そうなんですよ。私は私なりにキャリアを築いてきたのに、夫が売れたことで「売れない時代から公私にわたって支えてきた妻」とみなされるようになった。
- 渡辺
- 子育てと重なると、余計に…?
- 古舘
- そうなんです。育児でキャリアのペースが落ちると、「もっとやりたいのにできない」ってずっとモヤモヤしていました。でも2周くらいして、ようやく今は落ち着いてきました。
- 渡辺
- 何が転機で落ち着いていらしたのでしょう?
- 古舘
- ママ友の存在ですね。夫のことを知らない人たちが、ただ子どもの親として私と接してくれる。それがとても救いになりました。
- 齋藤
- なるほど、それで自分を取り戻せたんですね。
- 古舘
- そうですね。子どもの成長とともに、親の関わり方も変わってくるし。夫婦のバランスも、ずっと衝突しながら、すり合わせて、ようやく今は落ち着いてきた感じです。最近、子供が小学校に上がったんですよ。
- 渡辺
- おめでとうございます! 少し生活にも余裕が出てきましたか?
- 古舘
- そうなんです。ようやく手が離れてきて、少しずつ自分の時間が戻ってきました。
- 齋藤
- そんな今、 楽しみとか息抜きの時間ってありますか?
- 古舘
- 私、やっぱり「仕事したい人」なんですよ(笑)。何かを企画したり、考えたりするのが一番楽しいんです。コロナのときに偶然スケジュールが空いて、久々に歌舞伎を観たり、エッセイを書いたりして、あれはあれで良い息抜きになったと思います。
- 渡辺
- 素敵ですね。
- 渡辺
- ところで、理沙さんが落語にこれほどまで引き込まれる理由って、ご自身ではどんなふうに思っていらっしゃいますか? 言葉であらわすのは難しいかもしれませんけれど。
- 古舘
- これは15年のキャリアから辿り着いた一つの結論なんですけど、ちょっと大きな話になりますね。私は日本に生まれて、日本語を第一言語として育ってきたのに、27歳まで落語に出会わなかったんです。ラテン語までやってきたのに、生まれ育った国の文化に触れたことがなかった。その衝撃って、”植民地”を発見した!という感覚に近いんです。
- 齋藤
- それってつまり、自国の文化を“エキゾチック”に感じてしまったんですね?
- 古舘
- そうです。着物を着たおじいさんがひとりで舞台に出てきて昔のことを語ってる……それを見て”エキゾチック”だと思ってしまった。まるで”先住民”の踊りを遠くから見ているような感覚です。でも、それっておかしいですよね。日本の文化を、なんで西洋人のような目線で観ているんだろうって。
- 渡辺
- その違和感から、どんな問いに繋がっていったのですか?
- 古舘
- 「なんでこの国は、こんなに自国の文化を大切にしないんだろう?」っていう問いです。国立劇場の建て替えも進まない、文楽の研修生も集まらない。ピアノやバレエはひとつの街にいくつも教室があるのに、三味線や日本舞踊は、学年どころか学校レベルで習っているひとがゼロだったりする。これは構造的な問題があると思って、西洋と日本の「文化の位置づけの違い」を改めて学びました。
- 齋藤
- 文化の位置づけの違い、ですか。
- 古舘
- はい。私、西洋古典を学んできたので、たとえばギリシャ悲劇は、「政治の主体である市民」をポリスの一員として教育するための手段なんですよ。だから、市民権のあるものは、参加が義務なんです。異国の王様を演じたり、市民権のない女性を演じたりして、“演劇を通して他者を想像する力”を育てるんです。その流れがあるヨーロッパやアメリカでは、国が文化を支えますし、市民にも文化に携わるひとたちに対するリスペクトがある。
- 渡辺
- 一方で、日本の文化は?
- 古舘
- 日本の芸能は神事奉納といえば厳かに聞こえますが、稲作文化なので、天気といった人知のおよばぬものをつかさどる神様をよろこばせ、民たちのストレスを発散する非日常の場=祭で主に行われてきました。転じて、露悪的な言い方をすれば、時の為政者の“ご機嫌取り”によって発展してきた側面が大きいんです。芸能者の地位は低く、江戸時代に歌舞伎役者が千両、現在で1億円稼いだとしても、所詮は河原者。観客も、自分たちの日常には関係のない、下の存在として扱ってきました。近代以降も、その構造を引きずったままです。国が経済的に豊かで、たまたま熱心な政治家がいたから国立劇場を建てちゃったけど、伝統芸能を教育の基盤にしようという発想はない。だから制度も支援も手薄なんです。
- 渡辺
- 実は、どのジャンルの文化人の方々にお話を聞いても、「国として文化への認識が低い」と異口同音におっしゃいます。クラシックでも、漫画でも、邦楽でも。実際にオーケストラもバレエも国立のものはないですから。
- 古舘
- だから私は自分の課題として、日本の文化を“再発見”ではなく“自分たちの言葉で語り直す”ことをしたいんです。文化だけが共存可能だということ。経済は利害でぶつかるし、政治も常に対立がつきもの。でも文化だけは、国や民族、言葉、背景が違っても、理解し合えるし、感動できるし、共有できる。実際、私たちはピアノもバレエも楽しめるし、能や歌舞伎も外国人に受け入れられている。だから私は、この文化という領域に、これからの残りの人生をかけて向き合っていきたいと思っているんです。私は舞台に立たないけど、「語り部」として、文化の意味を届けていきたいんです。
- 齋藤
- それって、すごく希望のある視点ですね。
- 古舘
- 能や歌舞伎って、いまでも室町時代や江戸時代の形式を守りながら、現役で上演されている。そんな国、世界を見渡してもなかなかないんですよ。ヨーロッパの文化は“積み重ね”ではなく“上書き”なんです。ギリシャ悲劇を、当時そのままのかたちで今観ることはできない。シェイクスピアもそうです。でも、日本では能の舞台に、足利義満の時代の形式がそのまま生き続けている。これって、すごいことだと思うんです。
- 齋藤
- うわ、それもっと早く聞いてたら、能や歌舞伎をもっと楽しめたのに(笑)
- 渡辺
- その視点、まさに今必要な考え方だと思います。ぜひ本にまとめて発信していただきたいと切望してしまう。
- 古舘
- 書きたいんですけど、子育てや仕事もあってなかなか時間がなくて……でも野望と妄想だけはたくさんあります(笑)。
- 齋藤
- 編集スタッフとして手伝ってくれてる現役の湊さんも、せっかくだから古舘さんに何か聞いてみたら?
- 湊
- ありがとうございます。現在ICUに在学中の湊と申します。「今を輝く同窓生たち」のお手伝いをさせていただいております。古舘さんのお話、とても励みになりました。
私はずっと「好きなことを仕事にしたい」と思ってきたんです。でも、そもそも自分の“好きなこと”が何なのか分からなかったり、たとえ見つかっても「これで本当に仕事にできるのかな」って不安があります。古舘さんは学生時代、そういった悩みはありましたか?
- 古舘
- その話、すごく大事ですね。まずね、「好きなことを仕事にする」っていうのは、私はある意味リクルート的な罠だと思ってるんです。そこには「やりがい搾取」みたいな落とし穴もあるから、単純に“好き=仕事”にはしない方がいい。
- 湊
- なるほど。では、どう考えたらいいんですか?
- 古舘
- 私がオススメするのは、「好きなジャンルの中で、自分の“得意”を活かせることを仕事にする」ことです。たとえば私は落語が好き。でも、自分が高座に上がるタイプじゃないことは分かっていた。だから興行師という形で関わったんです。
- 齋藤
- 自分の得意をどう見つけるか、ですよね。
- 古舘
- そうです。それは周りをよく観察してみると分かることもあります。私の場合は、雑誌の編集部で、みんなが面倒がる経費精算が好きだったんです(笑)。項目ごとに分類してExcel入力して、レシート番号までちゃんと付けて出してたら、「そんな丁寧にやる人、他にいない」って言われて気づいた。つまり、他人は嫌がるけど自分にとっては苦じゃないこと――それって才能なんですよ。
- 湊
- 「自分が苦じゃないこと」って、案外大事なんですね。
- 古舘
- すごく大事です。たとえば写真撮って加工してSNSに上げるのが好きなら、それは広報やPRの仕事に向いてるかもしれない。人の話をずっと聞いても疲れないなら、取材や営業職も向いてる。そうやって「好きなジャンル×苦じゃないこと(=才能)」の掛け算で、自分の道を見つけるのがオススメです。
- 渡辺
- とっても具体的で、学生諸氏にとってすごくありがたいアドバイスですね。
- 古舘
- あと、「学生のうちに何をしたらいいか」ってよく聞かれますけど、私は本当に勉強しかしてこなかったんです。でもそれで全く後悔してない。ノートをまとめるのも、人に見せると「参考にならない」って言われるくらい自分流だったけど(笑)、でもそういう自分の方法で鍛えた事務力や分析力が、いまの仕事の土台になっています。
だから、「好き」だけじゃなくて、「自分が苦じゃないこと」「他の人より自然にできること」にも、ちゃんと目を向けてみてほしいなと思います。
- 湊
- なるほど……ありがとうございます。最後に私からひとつだけ、ICUでの4年間って、古舘さんにとってどんな時間でしたか?
- 古舘
- すごく楽しかったです。私、あの4年間が一番輝いてたと思います。体力も知力もあって、徹夜しても平気で、頭も冴えていて、世界をすごくクリアに見られていた。だからもし今、あの時の自分で国立劇場の再建に関われたら、もう劇場立ってたんじゃないかって本気で思ってるくらい(笑)。
- 渡辺
- 国立劇場、わたしも何とかしてほしいと切に願っているので、理沙さんには今からでも是非、再建に関わっていただきたいです。残念ながら、そろそろ時間がきてしまったので、最後に、今のICU生やこれからICUを目指そうと思ってくださる若い世代にメッセージをいただけますか?
- 古舘
- そうですね。斎藤さんもよく弟子の方に「人間力が大事だ」とおっしゃっていると思いますが、私はそれを“技術”だと思っています。人間力は生まれつき備わっているものじゃなくて、努力すれば誰でも身につけられる技術なんです。ICUのリベラルアーツ教育は、その「リベラル=自由」でいるための技術を磨く場所だと思います。すごく困難な時代だけど、それを自分の中に育てる時間として、このICUの4年間をめいっぱい使ってほしいなと思います。

プロフィール
2007年、東京・上野の鈴本演芸場で初めて寄席演芸と出会い、魅了される。29歳で出版社を退職。日本では数少ない寄席演芸興行師として、「いたちや」を立ち上げる。以来、伝統芸能と現代感覚を結ぶ活動を展開し、夫である講談師・神田伯山のマネジメントやYouTube番組のプロデュースなど、古典芸能の新たな発信にも積極的に取り組んでいる。
寄席演芸をはじめとした、日本の伝統芸能を次世代へとつなぐことを使命とし、講演や執筆活動も行う。現在は1児の母として育児と仕事に日々悩みながら、「文化の共存と継承」をテーマに多彩な活動を続けている。