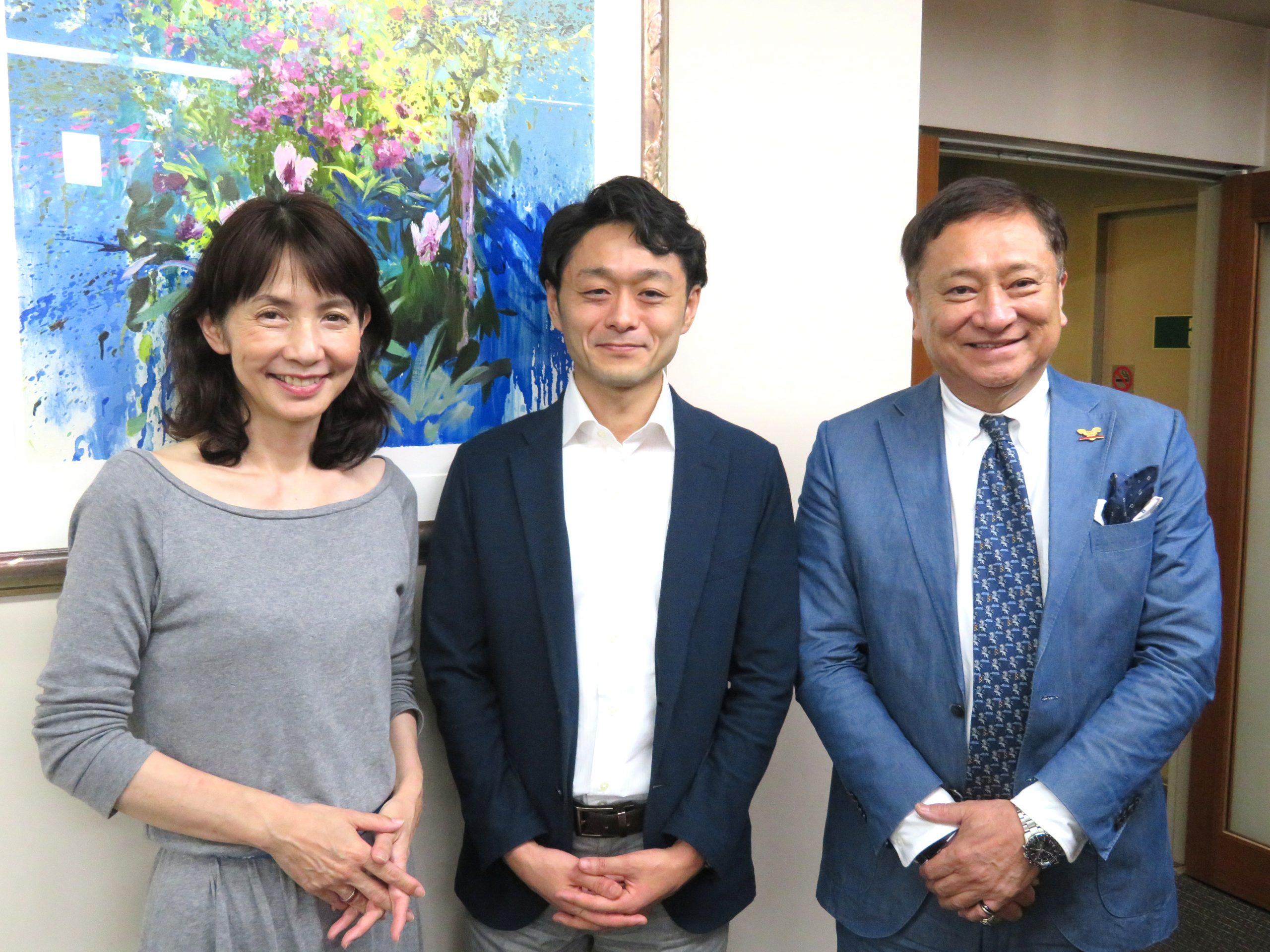ああ、びっくりした(笑)。
- 松崎
- わー。榎本さん(笑)。
- 齋藤
- 榎本さんは僕の本の編集担当だったんですよ。
- 榎本
- お忙しいのにお邪魔してすみません。
- 松崎
- 榎本さんは、ダイヤモンド社時代の先輩なんです。
- 渡辺
- そういうご縁が!今日が松崎さんのインタビューと聞かれて、わざわざ来てくださったんですね。松崎さんのお人柄ですね。
- 榎本
- (松崎さんは)私のダイヤモンド社での初めての後輩なんです。期待の新人で、将来が楽しみだと話していたんですけど、本人はダイヤモンド社を辞めてしまって(笑)。ダイヤモンドを辞めても、似たようなお仕事をしている人が殆どなのですけど、彼は全く違う分野で活躍していて、すごいね。
- 松崎
- ありがとうございます。
- 榎本
- じゃあ、またね!頑張ってね。
- 松崎
- ああ、びっくりした(笑)。
「私は明後日から春休みで、春休みを全力で頑張りたいと思っているから、ノーならノーで返事をくれないと困ります」みたいな凄い生意気な文を送ったのです(笑)。今思えば恥ずかしいですね。でも、そうしたら「明日朝8時に来い」と言われて。
- 渡辺
- 在校生の中には出版業界志望も多いと思うのですが、出版社ってとにかく狭き門ですよね?松崎さんは、どんなきっかけで受けられたのですか?
- 松崎
- SEAプロっていう留学プログラムが、1年生の夏の8週間と2年生の9ヶ月にあるのですが、当時ICU生でお付き合いしていた方が2年生のSEAプロで1年間海外に行くということになりまして。それで、恋愛どうこうではなく、置いてかれる感があるじゃないですか。向こうは1年間勉強して帰ってくるというところに。
- 渡辺
- 離れてしまうという意味ではなくて、向上心としてということで?
- 松崎
- はい。それで僕もやりたいことを頑張ってみようと思いまして。
それでドアを叩いたのが、あるフリージャーナリストの方のところでした。新聞社にアルバイトやインターンで入っても、クリッピングくらいしかできないと聞いていたので、個人のジャーナリストのもとで働ければ、色んなことをやらせてもらえるんじゃないかと考えたのです。
- 齋藤
- おお〜。
- 松崎
- 当時はインターンという言葉はそこまで浸透していなかったのですが、検索でウェブサイトを見ていたら採用のところに「インターン:現在募集していません」と書いてありまして。「現在は、ということは、いつか募集するのだろう」と考え、メールを何度も送ったのですが返事がありませんでした。電話をする勇気がなかったのですが(笑)。最後に「私は明後日から春休みで、春休みを全力で頑張りたいと思っているから、ノーならノーで返事をくれないと困ります」みたいな凄い生意気な文を送ったのです(笑)。今思えば恥ずかしいですね。でも、そうしたら「明日朝8時に来い」と言われて。
- 渡辺
- 通じてよかった!けれど、急に明日と?
- 松崎
- それでご縁をいただきまして。海外にも連れてっていただきました。
- 渡辺
- 授業との両立は大変ではなかったですか?
- 松崎
- 結構大変な職場でした(笑)。再来週から南半球の取材に連れてってやる、と言われたのですが、普通に学期中なんですよ(笑)。1週間ぐらいかと思ったら、少なくとも2ヶ月ぐらいと言われまして。単位を落としてしまうと話したら「自分で何とかしろ」と言われました。
- 齋藤
- へええ。
- 松崎
- まだ個人でパソコンを持つような時代ではなかったので、トンガのホリデイ・インホテルで友達に電話をして、レポートの内容を教えてもらいました。今でも覚えているのですが、ジェンダーの授業で、『クレイマー、クレイマー』っていう映画を見て、レポートを書けというものでした。Word で打ってメールで送信提出だったのですが、まずあらすじだけ聞いて。
- 渡辺
- ご覧になっていなかったんですね(笑)?
- 松崎
- あとでちゃんと観ましたよ(笑)。聞いたものから想像して、ホリデイ・インのレターヘッドがある用紙にレポートを書いて友達にファックスで送って、出してもらいました。それでCプラスいただきました(笑)。その時の授業は、全部通りました。
- 齋藤
- それはすごいね。
今思うとよくあの立場の僕に怒ってくださったなと思います。
- 松崎
- 当時は本当に死にそうになりながらやっていましたね。朝5時に起きて夜2時に寝るみたいな生活でした。本当に厳しかったです。
- 渡辺
- たとえば、どんなふうに厳しかったのですか?
- 松崎
- もう、学生と思ってないんですよ。自分と同じように働くものだと思ってくれていて。例えばその時4、5か国回っているのですが、当時、スマホもないし地図もないのです。でも「きみは運転手の役割もあるから地図は用意しとけ」って言われて八重洲ブックセンターに行って、行く街の地図を用意するわけですよ。でも、そこで手に入る地図の縮尺では信号なんか載っていないですよね。
- 渡辺
- 確かに。
- 松崎
- 当然ながらそんな縮図の地図はないのですが、現地に着いたら30分後に大臣のインタビューがあって、遅刻できないんです。にも関わらずそういうことに対してアドバイスはしてくれないので、「そこに連れて行く」ということを達成するために、必死に運転しました。序盤は連れて行くことができないこともあり、道をどうシミュレーションして準備するのが大事か、ということだけで1、2時間怒られました。でも、今思うとよくあの立場の僕に怒ってくださったなと思います。
- 齋藤
- それは偉いなあ。
- 渡辺
- インターンというより、サバイバルですね。
- 松崎
- そうですね。運転もですが、3食も僕が用意していましたし、ビデオのカメラを回すのも僕がやっていました。
- 渡辺
- え?ビデオも回していたのですか?
- 松崎
- きみのを使うことはないとは言われていたんですが、でも、何かあった時のために常に回しなさいと言われていました。僕が撮ったものも、ちゃんとその日の夜にチェックしてくれてダメ出ししてくれるんですよね。構図の切り方ひとつから。
- 渡辺
- 帰りたいと思うことはなかったですか…?
- 松崎
- 帰れなかったですからね。飛行機が2日に1便のような場所にも訪れたので、脱出しようにもできない(笑)。
「社会で埋もれているけど硬直化しておかしくなった制度を崩していく」という姿勢を学んだことが、今に繋がっているなと思います。
- 渡辺
- 海外での2ヶ月、かなり大きな学びがあったのでは?
- 松崎
- 社会人としての姿勢はそこで学びました。
- 渡辺
- こんなにキツかったらジャーナリストはもう諦めよう、とはならなかったですか?
- 松崎
- 取材活動自体は自分で執筆を行うものではなかったので、ジャーナリスト的な仕事を経験をした、という感じは自分はあまりなかったですね。その方の反骨心とか、みずから出入りがしにくくなるのを承知で体制の批判を表立ってできるだとか、「社会で埋もれているけど硬直化しておかしくなった制度を崩していく」という姿勢を学んだことが、今に繋がっているなと思います。
「君は我々をリスケさせて何をやってきたかまず説明しろ」と言われたのをよく覚えています(笑)。

- 渡辺
- そして、ダイヤモンド社に入社なさるわけですね?
- 松崎
- 当時を振り返ると、本当に自分は人間ができていなかった。未熟でめちゃくちゃでしたね。実はダイヤモンド社の最終面接も僕だけリスケしてもらっているんですよ。ダイヤモンド社の最終面接って、当時は役員全員による面接なんですよ。
- 渡辺
- それは…。
- 松崎
- 今ならわかるんですけど…役員全員集めるって大変なことですから。次が最終面接だとなったとき、その日程が授業で受けていた平和学のフィールドトリップと被ることがわかっていたのです。1年間かけて勉強してきて、最後が実習、という授業です。会社から電話をもらった時「合否を聞く前に答えてください。最終面接来られないかもしれないと言っていたけれども、来られますか?」と言われたんです。ちょっと卑怯だなと思いつつも、「はい」と言いました。そうしたら、面接は合格なので、いついつにきてくださいと言われました。納得できない気持ちをもちつつ、一旦は実習を諦めました。
フィールドトリップの直前の授業は、国境なき医師団の方にお話を聞く内容でした。それに感銘を受けて、やっぱりフィールドトリップに行きたいと思い、その直後に会社に電話をしたんです。そのときちょうど人事担当者がいなくて人事部長が出てくれて、こういう事情でどうしても納得いかないし、このまま入社できたとしても負の感情を持って入ることになってしまう、と言ったんです。ちょっと待ってなさいと言われて、2時間ぐらい待ったら「リスケしてあげる」と言われたんですよ。
- 渡辺
- 素晴らしい会社ですね。
- 齋藤
- そうやねえ。そんな会社はめったにないで
- 松崎
- 当然ながらリスケして受けた最終面接ではみなさん事情を知っているので、最初の質問が志望動機ではなく「あなたは我々をリスケさせて何をやってきたか、まず説明しなさい」と言われたのをよく覚えています(笑)。
- 渡辺
- フィールドワークでの体験を話されました?
- 松崎
- そうですね。週刊ダイヤモンドの元編集長だった方に、特集を1つあなたに預けるから、そのフィールドワークを記事にするとして、構成を語りなさい、と言われました。
- 渡辺
- なるほど。実際にフィールドトリップに行って、よかったですか?
- 松崎
- はい、よかったです。ユーゴスラビアに行きました。
- 渡辺
- 取材の件も含めたら、大学時代に相当な回数海外にいらしたことになりますよね?
- 松崎
- そうですね。普通の学生っぽくなかったのは確かです(笑)。寝ている時間もお金に変えたかったので、昼間もバイトして、夜はアジア人の学生寮に行って、そこの宿直のバイトをしていました。宿直は何か問題がなければ、寝られるので。それで、朝7時に起きてまた学校に行く、みたいなことを週3回ぐらいやっていました。
経営者の話を聞いた時に、なんで僕はあっち側じゃないんだろうって思い始めました。もうその時には事業をやりたくなっていたんだろうと思います。
- 渡辺
- ダイヤモンド社に実際に入ってからは、どうでしたか?
- 松崎
- すごく良い会社でした。入ってからの営業の研修で2日間過ごした井上さんという方が、すごく尊敬できたんです。平たくいうと、惚れてしまいました。それまで記者になりたいと言っていたのですが、営業を希望しました。
- 渡辺
- 井上さんのどんなところがお好きだったのでしょう?
- 松崎
- 誠実さです。すごくチャーミングなところもあったりして。当時は、人と話す時の癖やしぐさを真似していました。
- 渡辺
- 素晴らしい上司と巡り会えましたね。
- 齋藤
- それはいいことやなあ。
- 松崎
- そこから、ハーバードビジネスレビュー編集部の異動内示をもらいました。当時の僕にはチャレンジングな職場だったので、周りから相当心配されました。ただ、井上さんだけは将来、週刊ダイヤモンドに行きたいんだったら、絶対によいキャリアだし、そこで学べることはあるから行くべきだ、と言われたんです。それで、心が決まりました。
- 渡辺
- 念願の編集者であり、ジャーナリストという道ですね?
- 松崎
- ジャーナリストというよりかは編集者でした。編集長のかばんもちのような形で、マッキンゼーやBCGとか、世の中のそうそうたる頭脳が集まっているところに、右も左もわからないところに話を聞きに行けたのは、とても刺激的でした。立場のある方に若くして触れる機会をいただき、偉い人ほどとてもしっかりされているという印象を受けました。若手だからと軽く見られることもあったんですけど、トップの人は、どれだけ若かろうが、すごく丁寧に真摯に扱ってくれるんです。そういう姿にも惹かれましたし、立ち居振る舞いだとか、めちゃくちゃ勉強になりました。ただ、経営者の話を聞いていた時に、なんで僕はあっち側じゃないのだろうって思い始めました。もうその時には事業をやりたくなっていたんだろうと思います。
- 渡辺
- 編集者も、書いたり編集したりするというプレイヤーではありますけれど、経営面でのプレイヤーではないという意味ですね?
- 松崎
- そうですね。事業やりたいな、と思いました。
小学校の文集の内容が「僕の学校の先生たちがいかにイケてないか」という文章で、僕だったらもっとこういう先生になれる、というものだったんです。
- 渡辺
- うかがっていると相当なハードワーカーでいらっしゃるけれど、いつ頃からなのでしょう?
- 松崎
- 当時はそんな意識はしていませんでしたが、今思えば、自立したかったという気持ちが強くあったのだと思います。今思い出したんですけど、ICUも父親に内緒で受験してるんです。ずっとお金を貯めて、高校3年生で、バイクの免許をとったんですよ。バイクにどうしても乗りたかったんで。当然、すごく反対されましたけど、一応認めてくれました。でも、それで浪人しちゃったんです。当時は小学校の先生になりたくて、学芸大を受けていました。
- 渡辺
- 小学校の先生。それは、どこからきた夢だったのでしょうか?
- 松崎
- 先生になりたいというのは、小学生の頃からの夢でした。小学校の文集の内容が「僕の学校の先生たちがいかにイケてないか」という文章で、僕だったらもっとこういう先生になれる、というものだったんです。
- 渡辺
- へぇ(笑)どういうふうにイケてなかったのですか?
- 松崎
- 子どもの気持ちを考えられないとか、相手の身になって考えられないとか、学校の都合で子どもたちに要求をしてくるというところです。
- 渡辺
- こういう大人はちょっと嫌だな、という感じですね?
- 松崎
- はい、そうですね。
- 齋藤
- 子供の頃にそういうことを察知して、それを文章に表現するっていうのは、これはなかなかすごいことですよ。
- 松崎
- ただ、これを卒業文集に書いてしまったので、謝恩会で母親が担任の先生から嫌味を言われたらしいですけれども(笑)。
世の中には言葉とか文字とかになっていないと知られない、大事なことが隠されていることがいっぱいあるんだなと思って、そういうものを知らせる人になりたいと思いました。
- 渡辺
- 松崎少年としては、先生への批判を卒業文集に書いたらやばいかも、とは思わなかったんですね(笑)?
- 松崎
- 思わなかったです。そういうところに気が回る感じではなかったんだと思います。
- 渡辺
- なるほど。じゃあ、イケてる小学校の先生になるんだという夢から、ジャーナリストを志したのはどういうきっかけだったのでしょう?
- 松崎
- 学芸大が、一次二次って二回あって、センター試験がボーダーよりやや上だったんですね。二次は小論文と面接だけだったんですよ。ボーダーいっていて落ちるっていうことは、よほど面接と小論文が悪かったということですよね。面接は準備不足で答えられないこともあったのですが、小論文も書けなかったので、まず小論文をしっかり学びたいと思ったのです。
それで浪人して予備校に行ったときに、教育系と社会科学系の小論文という授業があったのですが、間違えて社会科学系の小論文の授業をとってしまって。当時、新聞は受験対策で読んでいたのですが、本はろくに読んでいなくて。授業で当時受験生の名著とされていた『エビと日本人』を読んでびっくりしたのです。日本人が食べるエビが遠くのマングローブを壊しているという話です。1年間は受験勉強をちゃんとやってきていましたが、そんなことどこにも書いてなかった。世のなかには言葉とか文字とかになっていないと知られない、隠されている大事なことがいっぱいあるんだなと思って、そういうものを知らせる人になりたいと思いました。それが、ジャーナリストだったのです。本質的に大事なことが見えなくなっていることを表に出して、改善したい想い、それは今も同じですね。
- 渡辺
- 根底にその思いがあるんですね。
自分の受験番号があるのが見えて、本当に嬉しくて、どうしていいかわからなくて、とりあえず走りに行こうということで、ろくに運動もしてなかったのもあって、10キロも走って帰ってこられなくなったんです。
- 渡辺
- ICUを目指したのは、どうしてだったんですか?
- 松崎
- 実は姉が教えてくれたんです。姉は芸術関係の学校に行きたくて、日芸とかを受けていたのですが、落ちて専門学校に行かされてしまったんです。次に僕がいたのもあって、浪人させてくれなかったんです。それで僕に恨みを持っているのではないかと思っていたのですが、僕がジャーナリストになりたいと言ったときに、これ知ってる?とICUのパンフレットをくれたんです。そこで初めてこんな学校あるんだと知りました。それで、こんな勉強したいな、とか、海外で働きたいし英語を叩き込んでくれるなら、ということで良いなと思い、ICUを受けることにしました。親に内緒にしないといけないので、バイクを売って受検費用に充てました。
- 渡辺
- どのタイミングで、ご両親にバレましたか?
- 松崎
- 母親には途中でバレて、知られていました。合格発表は見に行かなかったので電報で来たのですが、自分の受験番号があるのが見えて、本当に嬉しくて、どうしていいかわからなくて、とりあえず走りに行こうと思い立ちました。浪人生でろくに運動もしてなかったのもあって、10キロ先くらいまで走って帰ってこられなくなったんです。
- 渡辺
- 嬉しさのあまり。
- 松崎
- 電話して父親が迎えにきて、なんでこんなところまで走ってきたんだと言われて、そこで受験のことを告げました。父はICUのことを知らなかったので、家に帰って姉と一緒に説明しました。
- 渡辺
- 反対はされませんでしたか?
- 松崎
- されなかったです。ただ、そのとき筑波大学も出願していたので、そこは受けるんだよな?と聞かれました。でも、受かったら行かされるのがわかっていたので、受けませんでした。
男の受験が控えているのだから、女のお前はダメだ、というのは変だな、と思いました。
- 渡辺
- 松崎さんは、ご両親を尊敬していらっしゃいますよね。それは、いわゆる雷親父というわけではないんですよね?
- 松崎
- 父親は優しかったのですが、彼の価値観と私の価値観で真逆の部分があり、お互いに折れたくない部分があったのだと思います。
- 渡辺
- すごく尊敬しているんだけど、ここは相入れないな、というところを感じていらした?
- 松崎
- ありました。姉を浪人させず専門に行かせたのはすごく衝撃でした。
- 渡辺
- お姉さまの思う道を進ませてあげたい、という気持ちが弟としてあったのでしょうか。
- 松崎
- それもですが、男の受験が控えているのだから、女のお前はダメだ、というのは変だな、と思いました。
- 齋藤
- 学校の先生はこうしたほうがいいんじゃないかと書いたり、本を読んで、うわあ、こういうことを文章で表現しておくことが大事だと、子どもの頃に考えておられるのはすごいですね。ダイヤモンドセレクトでお受験をする母親向けに記事にも書いたのですが、いい大学に行けば、いい会社に入れば安泰であるというのは間違った考えですよ。本当はその都度、今の状況に対して、疑問を抱くような子どもたちを育てていかなければならないのですよね。松崎さんみたいにね。
- 松崎
- 理路整然ではなかったですが…(笑)。
- 齋藤
- でもそういう考えをもてるのは、どこからきているのかっていうと、やっぱり親だと思うんですよ。
- 松崎
- そう言われてミサンガ事件を思い出しました。私が小学校5、6年生ぐらいのとき、ある日学校にミサンガをつけていったんです。今では当たり前になりましたが、当時はそうではなくて、学校に行ったら先生に外せと言われて、切るしかなかったんですね。それに父が抗議して、先生に会いに行ったんです。だから、反骨心みたいなのは意外と間近に見ていたのかもしれないです。
大人たちが飲み会で子どもたちのサッカーについての話をしないで、ビールを飲んでいるのも納得いかなくて、飲み会でこそ、サッカーの指導の話しましょうよ、と言ったりもしていました。
- 渡辺
- 反抗期はありました?
- 松崎
- ありましたね。中高生ぐらいの頃に。
- 渡辺
- けっこう激しかったですか?
- 松崎
- 実はずっとサッカーをやっていました。小学校1年生の時に仲良しだった子と、サッカー漫画を真似てサッカーチームを作ることにしたのです。父にサッカーチームを作ると言ったら、俺がコーチになってやると言って、数週間後くらいにはちゃんとした登録チームになっていたんです。数ヶ月後には近所の小学生3、40人くらいが我が家に集まって、クラブ名をきめたのを覚えています。小学校時代はそこでプレーをしましたし、中高では部活がない時にお手伝いをしていました。
父親は、そのクラブの理念として、競技力を高くすることを目的にしないでのびのびとやり、自己の気づきとか成長を促していこう、と話すのですが、話している理念と、実際の練習やコーチの声かけにものすごいギャップがあったんですね。それが中学生くらいから許せなくなってですね。毎週ノートに文字と図で、こういう風にするべきだとか、自分だったらこうしたいとかを書いては、父親に話したんです。
- 渡辺
- すごくまじめですね。
- 松崎
- でも、大人の事情ではぐらかされるのですよ。みんなボランティアだしとか、仕事あるしとか。受益者は子どもだから、それができないんだったら、そこをやらせてくれといって、時間は限定的だったけども、指導をしていた時期もありました。あとは、大人たちが飲み会で子どもたちのサッカーについての話をしないで、ビールを飲んでいるのも納得いかなくて、飲み会でこそ、サッカーの指導の話しましょうよ、と言ったりもしていました。
- 齋藤
- 昔のことをしっかり覚えておられるんですね。それも、ちゃーんとまとめられてるんだよなあ。
やっぱり反骨心、とはいえありたい姿は持っているので、そこを両輪で苦しくても貧乏でも徹夜してでも回して行くというところは僕の強みですね。
- 齋藤
- 今のこの路線で考えていくと、そういう若かりしころがあって、それでダイヤモンド社に入り、そのあとベネッセにいかれて、そして今の日本ブラインドサッカー協会。
- 渡辺
- 今は一番やりたいことをなさっているのですよね?
- 松崎
- その実感もありますが、惑いもあります。この業界で、名刺も受け取ってくれないようなところから始めて、今は障害者スポーツ界でも一目置いてもらっていることを感じます。そうなると、守りが大事な組織になってくるので、いかにミスをしないようにするかとか、コンプライアンスを守るかというところの方が大きくなってきて、反骨心といった強みを活かせる場所ではないなという気はしているんです。スポーツ界は昨今、役員の任期上限なども定めていることもあり、自分自身辞める時期というのはよく考えます。むしろそこはお二人に相談にのっていただきたいぐらいです。
- 渡辺
- いま、あえて言葉にするとするならば、松崎さんの強みはどういうところだと思われますか?
- 松崎
- やっぱり反骨心。とはいえ、ありたい姿も描き持っているので、苦しくても貧乏でも徹夜してでも、その両輪で回して行くというところは僕の強みですね。
2度と記者の職に戻ってくるなよ。その覚悟があるんだなと言われ、はいあります、と言って、追い出していただきました。
- 渡辺
- ダイヤモンド社を出てベネッセに行くという節目では、思い切りましたか?それともいいタイミングでしたか?
- 松崎
- 会社に不満もなく、みなさん応援してくれたので、よかったと思っています。
- 渡辺
- それはみなさんに丁寧にお伝えして、丁寧な辞め方をしたということでしょうか。
- 松崎
- 怒られましたね。あれだけ週刊ダイヤモンドに行きたいと言っておきながらベネッセとはなんだと。あそこは記者じゃないぞ。事業会社だぞと。採用してくれたときの役員にまで呼び出されて、週刊ダイヤモンドに配属されるよう働きかけてあげるから残れって言われたんです。
- 齋藤
- かなり期待されていたのだねえ。
- 松崎
- 今思えばそうだったんだなと思います。
最後、その方に言われたのは、それでもやめると言うなら、2度と記者の職に戻ってくるなよ。その覚悟があるんだなと言われ、はいあります、と言って、追い出していただきました。きっと、よい意味で退路を断ってくださったのだと思います。
- 渡辺
- 戻りたくなるかもしれないとは思わなかったですか?
- 松崎
- あまり考えてなかったです(笑)。
29歳だし好きなことをまだやろうと思いまして。当時お手伝いしていたブラインドサッカーに全力を注げば、何かを変えられるかと思ったのです。
- 渡辺
- ベネッセには1年?
- 松崎
- そうです。きちんとルーチンに則って仕事をすることでパフォーマンスをあげていく、ということが求められる会社でした。本当に大きく、成熟した会社なんだなと思いました。ただ、ベネッセでは始末書の山になってしまって、全然向いていませんでした。
- 渡辺
- 始末書の山?
- 松崎
- 気軽に書いてしまってました。なにか事故があっても、どちらか片方が100%悪いということはないと思っていたのです。相手方も書いているんだろうなと思っていたら、僕しか書いていなくて。でも始末書を書かないためには、同じ会社の違う部署の人と責任のなすりつけ合いをしないといけないわけですよ。そういうのは合わなかったですね。
- 渡辺
- じゃあもうやめよう、とすぐに思い立ったのですか?
- 松崎
- それでもがんばってはいたつもりでした。新規事業開発室という、教育を語らない会社が教育を語る、という視点の事業でした。体験学習やキャンプや化学実験教室などを企画していたチームでした。しかし、当時の社長がスキャンダルで即日退任、という目に遭い、その数日後にはこの部署自体が解散になってしまいました。大企業は、事業自体が良いかどうかではなくて、誰がやっていたのかということで事業がなくなってしまう場合もあるのだと痛感しました。それで、大企業への憧れがなくなったような気がします。それで、28歳だし好きなことをやろうと思いまして。当時お手伝いしていたブラインドサッカーに全力を注げば、何かを変えられるかと思ったのです。
周りからは無理だからやめろと、業界の人ほどストップをかけてくださいましたね。でも、そのやめろというのも力になっていたのかもしれないです(笑)。
- 渡辺
- そこからずっとブラインドサッカーに携わっていらしたのは、やはり惹かれるところがあったのでしょうね。
- 松崎
- はい、もう魅力の塊でした。
- 渡辺
- どういうところが魅力なのでしょう?
- 松崎
- もともとは、マイノリティの人たちに思いを馳せるような人間ではなかったのです。同級生に視覚障害者がいましたが、一言も口を聞かずに卒業するぐらい無縁な感じでした。その原体験は小学生の時にあって、障害学級の子と手を繋いで遠足などに行くという状況が定期的にありました。背の順で1番前から3番目位の人が手を繋ぐ担当でした。僕は背の順でいつも一番前だったので、自分の中では「チビの罰則規定」のような印象で障害者と付き合う、という感じが嫌でした。完全に偏見の塊だったんです。でも、機会があってブラインドサッカーの場所に行って、目隠しして、プレーしてみたんです。ガシャガシャ音の鳴るボールを見えない人にパスするには相手の声が必要で、相手がパスをこっちに出すには僕の声が必要なのです。頭で考える余裕はなく、とにかく一生懸命声を出して、声を聞いて、を夢中で繰り返して3、40分やりました。その間、相手が障害者だということは全く考えていなくて、始めて心がフラットな状態で接せられたと感じました。スポーツのような出会い方であれば、スティグマを持っている者であっても、心の鱗が取れるような体験ができるんだなと思ったのが原体験ですね。
- 渡辺
- このブラインドサッカーだったら情熱をかける意味がある!と思われたのですね?
- 松崎
- そうですね。ただ、障害者スポーツの競技団体では、当時だれもお給料をもらっているような状況ではなかったです。みんなボランティアでした。事務所は会長さんの住んでいるマンションに登録、のような時代でした。だから、ブラインドサッカーでこういうことやりたいといっても、周りからは無理だからやめろと、業界を知る人ほどストップをかけてきました。でも、そのやめろというのも力になっていたのかもしれないです(笑)。
ダイバーシティの概念を、ピッチの場に出るとすごく肌で感じるんですよね。お互い生かし合ってこそ、勝ったり負けたりするので。共通のゴールに向かって、立場を超えなきゃいけないので。
- 齋藤
- 理事長の方とかおられたと思うんですけど、松崎さんを何で評価してもらえたんでしょうかね。
- 松崎
- 当時の事務局長の方は視覚障害スポーツの中ではすごく実績のある方で、価値観が固まった人なのではないかと思っていたのですが、お酒を飲むとすごいフラットな人で、「あなたみたいな人がこの業界を変えられるのかもしれないね」と言ってもらえました。でも、彼からすると、生意気に意見をする若者は過去に何人もいたみたいで、でもみんな、家庭が忙しくなった、仕事が忙しくなった、とやめていったそうなんです。僕も出版社で働いていたから、締め切り近くになると連絡取れなくなっていたんです。松崎くんだって連絡取れなくなるときあるじゃないか、それで大丈夫か、と言われました。
それを受けて、ある時、当時の理事の皆さんに、自分の考えを説明する機会がほしいと言ったんです。会議の場で提案させてもらって、それでダメだったら、地道に現場活動を頑張ります。でもそれで認めてもらえるのだったら、一個ぐらい好きなことをやらせてくださいという思いでした。
それで、それから1年間くらいで、月に2、3人ぐらい、誰でもいいからブラサカの魅力を語ることを自分に課しました。始めは、すごいんだよこのスポーツ!としか言えず、これじゃ会話が5分ももたないんです。その「すごい」っていうのはどういうところなのか、大学の同級生とか一人ひとり捕まえて話していたんですけど、話していくうちに自分なりに魅力が見えてきたりもしました。
- 渡辺
- 例えば、どんなふうに語ったのですか?
- 松崎
- 「障害者を助けてあげる」みたいな観点が当時強かったんですよね。でも、話しているうちに、彼らが生きやすくなる社会って、実は自分自身だって救われるんじゃないの、という観点が見えてきたのです。ダイバーシティの概念を、ピッチの場に出るとすごく肌で感じるんですよね。お互い生かし合ってこそ、勝ったり負けたりするので。共通のゴールに向かって、立場を超えなきゃいけないので。
- 齋藤
- 彼のようなタイプは、基本的に日本の大会社じゃ難しいのですよね。保守的な大会社は安定することが重要ですから、新しい波風を立てる人は基本的に嫌われるのですよ。彼は現状に対して疑問を提示するようなことをやってきていますよね。普通はこれをやると嫌われるのですよ。ところがね、ブラインドサッカー協会はエスタブリッシュされていないから、危機感を持ち始めて、いっちょまえなことをいう若者に対して、こいつならいけるかもしれへんって思ったのだろうね。大きな組織は波風立てる人は嫌われるけど、危機感のある組織は、彼のパワフルさを評価するのかもしれないね。
無理だからやめとけっていわれていたのですが、それを無視して成功しました。
- 松崎
- 専従してからは、、本当に極貧生活を味わったなと思います。貯金も全部切り崩して。娘の使っていたよい匂いのする消しゴムとか食べられないかな、とか考えた日もあった(笑)。
- 渡辺
- それは、ブラインドサッカー協会に入ってどれくらいの時期に?
- 松崎
- 2〜3年が事業化するまでの山とよく聞くのですけど、私の場合、もっとながかったですね。子どもの保育園の費用を支払うのも大変でした。
- 渡辺
- それでもしのいで、やっていこうと思われたのですね?ダイヤモンド社での約束はあっても、やろうと思えば、元の職場に戻ることも出来たかもしれないわけですから。
- 松崎
- 飯を食うよりも、ここで実現したいという欲の方が強かったですね。たまたま以前お世話になった方に電車で会って、どうせすぐ食えないだろうから編集者の仕事を
発注してあげるよと言われて、実際1年くらい仕事をもらっていたんですよ。でもある時、メンター的な方に「進捗が悪いよね、本当にここにフルコミットしてるの」と言われてしまいました。なんのために辞めたのかって、120%睡眠を削ってでもやるって決めたからなのに、これではダメだと思い、その足でお世話になった仕事をいただいた人のところにいって、3ヶ月後に仕事を辞めさせてくださいって言いました。めちゃくちゃ怒られましたけど。
- 渡辺
- なるほど。食べていけるようになった道のりも教えてください。
- 松崎
- 社会に価値を見える状態にして、きちんと伝えれば、価値を受け取ってくれた人からいずれお金や人やものとなって戻ってくるだろう、と気づいたことでした。助けてくださいというお願い営業は一切やめましたし、日本代表頑張っているんで寄付してくださいとかも一切やめました。これはいまでも僕のポリシーです。価値を提供できれば、いつか還元されていくと信じ続け、それで還元されるまでに5-6年かかったという感じです。
- 渡辺
- 還元され始めた時の手応えはどうでしたか?
- 松崎
- そうですね、話を聞いてくださる方が増えましたし、業界の中でも無下にされなくなりました。2014年に、世界でも珍しいのですが、単一の障害者スポーツ、単一大会での有料化に踏み切って、お客さんが満員になったんです。その企画の時も、それを聞いた業界中の方々から、またそんなのやるの、無理だからやめとけ、といわれていたのですが、うまくいくことができました。業界的には、それをきっかけに無視できなくなったんだろうな、という印象をうけました。無視できなくなると、影響力も出てきますし、会議にもちゃんと呼ばれて、こっちが発言する気なくても、発言を待ってくれたり。あ、ちゃんと実績があれば、こういう風になるんだなっていうのを肌で感じたのが14年15年という感じです。オリパラも13年11月に決まって、14年くらいまで落ち着いていましたけど、15年くらいからはやっぱりだいぶ世の中の状況変わってきたので、いい外部環境にも恵まれたんだなと思います。
- 渡辺
- 日本ブラインドサッカー協会をここまで育てた実感が湧きますよね。
- 松崎
- そうなんですけど、やっぱり、このコロナの状況で相当事業は厳しい状況なので。今はちゃんとそこに向き合う時期だろうなと思っていますね。
大会をちゃんと安全に管理して、再開して、そのかわり、そこに価値をみてくださって、お金が回る仕組みにしていきたいなと思っています。
- 渡辺
- コロナ感染拡大の影響は、どのように出ているのでしょうか?
- 松崎
- 基本的に密ばかりの事業で、企業研修や子ども向けの体験学習が、全部止まっています。そしてこれは年間の見込みでスタッフを確保しているので、結構リスクがあります。世の中からコロナで障害者がいなくなるわけではないので、我々が進めていきたい「混ざり合う社会」という理念に向かっていくプログラムを開発しながら、どう担保して行くかというのが、一番チャレンジしているところですね。
- 渡辺
- 正念場ですね。
- 松崎
- 寄付してくださいというのもいいんですけど、俯瞰してみると、相対的な貧困の学習層であったりだとか、寄付はそういうところに回ったほうがいいなと思っています。変な話、ブラサカのアスリートたちはまだ恵まれているほうだなと思っているので、そういうものではなくて、大会をちゃんと安全に管理して再開して、そのかわり、そこに価値を見出してほしい、その上でお金が回るように再開していきたいなと思っています。
今そう感じられているのは、あのディスカッションとも言えない、友だちとだべったあの空間ですよね。
- 渡辺
- 最後に、ICUの在校生や、これからICUを目指そうとしている若い世代にメッセージをお願いします。
- 松崎
- ICU時代を振り返って一番に思い出すのは、友だちとだべっているシーンです。だべっている内容はくだらないこともあれば、世界の平和とかについても語ってしまうのがICU生ですよね。僕は今、ブラインドサッカーというすごく具体的で個別的で、狭い領域で仕事をやっているように思う人もいるかも知れません。でも、この仕事は平和や公平さってなんだろうと世の中に問うことでもあると思うし、普遍的な価値を考える仕事だとも思っています。今そんなふうに感じられるのは、あのディスカッションとも言えない、友だちとだべったあの空間のおかげだと思います。今はコロナの影響でそれができないと聞いていて、学生たちも大変だとは思います。でも、生身の議論をして、その人がどんな表情で話しをしているのかとか、ディスカッションから喧嘩してしまうとか、そういう青臭いことに真正面から向き合えた特別な4年間でした。それが今の原点だと思っています。早く通学が再開され、そんな状況が戻っていくことを願っています。
プロフィール
松崎英吾(まつざき えいご)
日本ブラインドサッカー協会専務理事兼事務局長。1979年生まれ、1999年ICU入学。在学中にブラインドサッカーと出会い、卒業後はダイヤモンド社に入社。営業や雑誌編集に携わりながらブラインドサッカーの体験会などを企画。2007年に協会事務局長となって脱サラ。視覚障害者と健常者が当たり前に混ざり合う社会を目指して奮闘中。